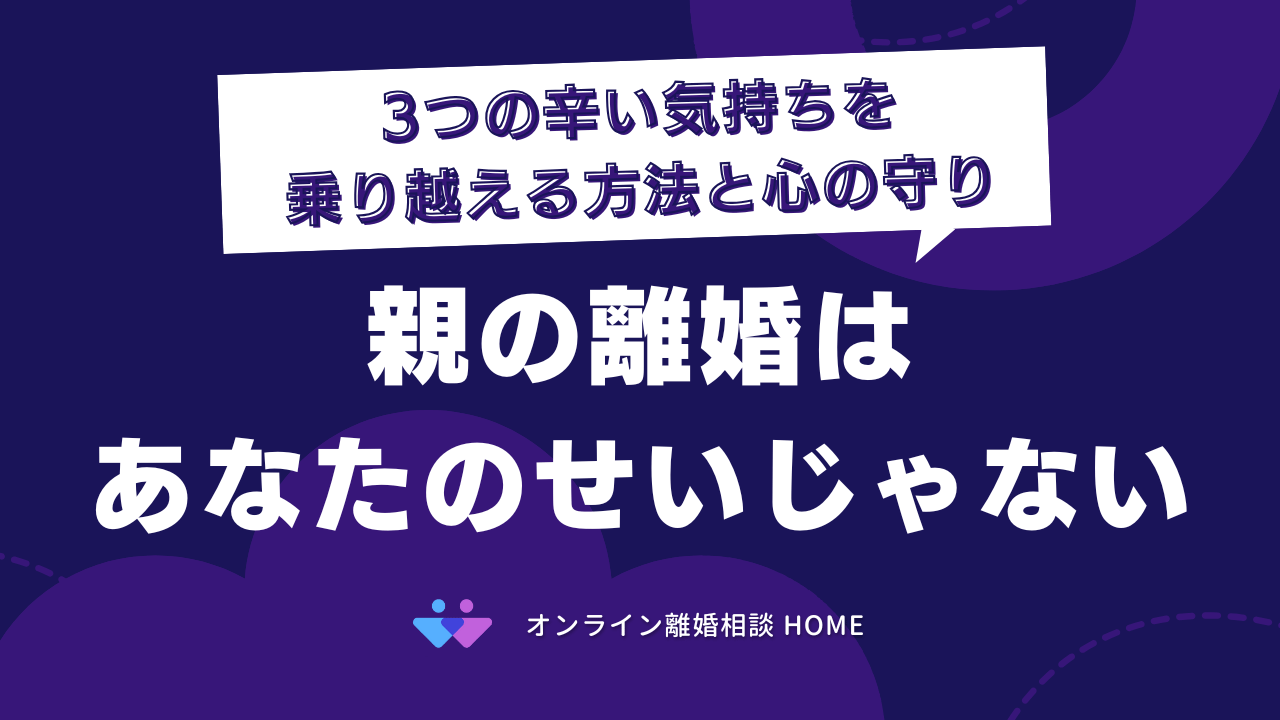「親が離婚したら自分の人生はどう変わるんだろう…」
「本当はすごく辛いのに、誰にも話せない…」
そんな不安や悩みを一人で抱えていませんか。親の離婚は、未成年・成人を問わず多くの人にとって突然の大きな出来事です。家族や進路、これからの人間関係まで、すべてが不透明に思えてしまう瞬間があるでしょう。
でも大丈夫です。親の離婚を経験しても、あなた自身の価値や未来は変わりません。
大切なのは「感情を素直に認めること」「親の問題と自分の人生を切り離すこと」「一人で抱え込まず誰かに話すこと」。
この3つを意識するだけで、心の重荷は少しずつ軽くなっていきます。今抱えているモヤモヤや将来への不安は、決してあなただけのものではありません。
この記事では、親の離婚に直面した方や、どう乗り越えたらいいか迷っている方に向けて、主に以下を専門家視点でご説明します。
- 親の離婚が子どもに与える心理的・生活面の影響とその対処法
- 気持ちの整理や家族との向き合い方、親の再婚や相続などの実務的なポイント
- 同じ経験を持つ人の体験談やよくある疑問への回答
あなたがどんな立場にいても、この記事を読むことで「自分の未来は自分で選んでいいんだ」と前向きな気持ちになれるはずです。辛い今を乗り越えるヒントを、ぜひ参考にしてください。


親の離婚が子どもに与える影響【年齢別に解説】
親の離婚は、子どもにとって大きな環境の変化をもたらします。
「自分の家庭が変わってしまうのは怖い」「もしかして自分のせいなのかもしれない」と、不安や戸惑いを抱える子も少なくありません。
特に子どもの年齢や発達段階によって、受ける影響や感じ方は異なるため、周囲の大人が適切にサポートしていくことが大切です。
子どもは離婚という出来事をどのように受け止めるか、年齢ごとに特徴があります。
幼い子ほど環境の変化に敏感であり、思春期には将来への不安や家族観への影響も現れやすいです。
「子どもの心にどんな変化が起きているのだろう」と悩む方も多いでしょう。
以下で、親の離婚が子どもに与える具体的な影響について、年齢別に詳しく解説していきます。
①精神的な影響:「自分のせいかも」という罪悪感
親の離婚は、子どもに精神的な負担を与えることがあります。
特に多いのが「両親が離婚したのは自分のせいではないか」と感じてしまう罪悪感です。
親の喧嘩やすれ違いを目の当たりにすると、「もっといい子でいれば、パパとママは別れなかったかもしれない」と自分を責める気持ちを抱きやすくなります。
このような罪悪感は、幼児期から学童期の子どもによく見られます。
また、子どもが大人に気を遣い、感情を抑えてしまうこともあります。
罪悪感が強いまま成長すると、自己肯定感の低下や人間関係への不安につながる場合があるため、周囲の大人が「あなたのせいじゃないよ」としっかり声をかけてあげることが大切です。
親や周囲の大人が、子どもに寄り添い、適切にフォローすることで、罪悪感や精神的な負担を和らげることができます。
②生活面での影響:経済状況の変化や転校など
親の離婚は、子どもの生活環境にも大きな影響を及ぼします。
特に経済状況の変化や住居の移動、学校の転校などが発生しやすく、「友達と離れたくない」「今までの暮らしが変わるのが不安」と感じる子どもも多いです。
生活面での具体的な影響には、以下のようなものがあります。
- 経済的な変化:
離婚によって家計が一方の親の収入だけになると、生活水準が下がったり、習い事や進学の選択肢が限られることがあります。 - 住環境の変化:
離婚後に引っ越しや転校が必要になるケースも多く、新しい環境に慣れるまでストレスを感じやすい傾向があります。 - 家族構成の変化:
片親とだけ暮らすようになり、日常の会話や生活リズムが大きく変わることもあります。
このような生活面での変化は、特に学童期の子どもにとって大きなストレスとなることがあります。
新しい生活に慣れるためには、親が子どもの気持ちを丁寧に聞き、できるだけ安定した日常を保てるよう心がけることが大切です。
③将来への影響:自身の結婚観や家族観の変化
親の離婚は、子どもの将来の結婚観や家族観にも影響を及ぼします。
思春期以降になると「家族はまた壊れてしまうのでは」「結婚しても幸せになれないかもしれない」と将来に対して不安を抱くことがあります。
離婚を経験した子どもは、次のような影響を受ける場合があります。
- 家族に対する不信感:
両親の離婚をきっかけに、家族関係や結婚に対する理想が持てなくなることがあります。 - 自分自身の結婚に消極的になる:
「自分も両親のようにうまくいかないのでは」と、結婚やパートナーシップに慎重になる場合もあります。 - 自立心が強まることも:
一方で、「自分の人生は自分で決めたい」と前向きな意欲が生まれるケースもあります。
こうした将来への影響は、子どもが成長して社会に出る時期まで続くこともあるため、親が早い段階から子どもの不安や疑問にしっかり向き合うことが大切です。
【年齢別】幼児期・学童期・思春期の影響の違い
親の離婚による影響は、子どもの年齢や発達段階によって現れ方が大きく異なります。
それぞれの時期でどのような影響があるのかを理解しておくことは、適切なサポートにつながります。
年齢や発達段階ごとに適切な声かけや支援を行い、子どもの気持ちに寄り添うことが、安心して成長していくための鍵となります。

辛い気持ちとの向き合い方|自分を守るための3つの方法
親の離婚に直面したとき、「どうして自分ばかりこんな目にあうんだろう」「この気持ちをどうしたらいいかわからない」と感じる方もいるでしょう。
誰にでも言えない不安や悲しさを抱えることは、決して特別なことではありません。
そのようなときは、自分の心を守るための方法を知り、少しずつ気持ちを整理していくことが大切です。
自分の感情を否定したり、「我慢しなきゃ」と思い込んだりすると、かえって心の負担が大きくなってしまいます。
「このままでいいのかな…」と感じるあなたも、自分らしく前を向けるよう、できることから始めてみましょう。
ここでは、辛い気持ちと向き合い、自分を守るための3つの具体的な方法を紹介します。
①「悲しい・辛い」自分の感情を否定しない
悲しい、寂しい、腹が立つなど、親の離婚によって生まれる感情はどれも自然なものです。
「こんな気持ちになるのはおかしいのかな」と悩む必要はありません。
むしろ、その感情を否定せず、きちんと受け止めることが心の回復への第一歩となります。
感情を押し殺すと、後からもっと大きなストレスや落ち込みにつながることもあります。
「自分は今、こう感じているんだ」と素直に認めてあげることが大切です。
日記を書いたり、信頼できる相手に話したりすることで、気持ちが少しずつ整理されていきます。
- 感情の言語化:
言葉にすることで、漠然とした不安や悲しみが整理されやすくなります。 - 泣きたい時は泣く:
無理に我慢せず、心のままに感情を表に出して大丈夫です。
あなたの気持ちに正直になることで、心が少しずつ落ち着いていくはずです。
②「親の離婚」と「自分の価値」を切り離す
親が離婚したからといって、あなた自身の価値が変わることはありません。
「自分がもっとしっかりしていれば」「自分は愛されていないのかもしれない」と思う必要はないのです。
親の関係は親自身の問題であり、子どものせいではありません。
厚生労働省の調査でも、多くの子どもが「離婚は自分の責任だ」と感じてしまう傾向がありますが、事実として責任を感じる必要はありません(厚生労働省「子ども家庭福祉の現状」2023年)。
親の離婚とあなたの価値は全く別のものだと、何度でも自分に言い聞かせてください。
③信頼できる大人や相談窓口に話してみる
一人で悩み続けると、心の負担がどんどん大きくなってしまうことがあります。
そんな時は、信頼できる大人や相談できる場所を頼ることも大切です。
学校の先生や親戚、カウンセラー、スクールソーシャルワーカーなど、あなたの話を親身になって聞いてくれる人は身近にいます。
「こんなこと話してもいいのかな」と思うかもしれませんが、困っている時に助けを求めることは勇気ある行動です。
一歩踏み出して話してみることで、新しい気づきや安心感を得られるでしょう。

離婚する両親とどう向き合う?子どもができること
親の離婚という現実を前に、「どうすればいいんだろう」「何を話せばいいのかな」と迷っている方もいるはずです。
親のことを思うあまり、自分の気持ちを抑えたり、無理にどちらかの味方になろうとしたりする子も少なくありません。
そんな時は、自分自身の心を守りながら両親と向き合う方法を知っておくことが大切です。
あなたにしかできない役割や、あなたにしか感じられない気持ちがあります。
「こんな時、どうやって親と接すればいいの?」と感じているあなたのために、子どもができることや心がけたいポイントを解説します。
以下で、離婚する両親と向き合うための具体的なヒントを紹介します。
離婚を告げられた時の心構え
離婚を告げられた時、驚きや悲しみ、怒りや混乱などさまざまな感情が一気に押し寄せてくることがあります。
「どう受け止めたらいいかわからない」「自分はどうしたらいいの?」と思う方もいるでしょう。
その気持ちは決して間違いではありません。
最初は無理に理解しようとせず、感じたままの気持ちを大切にしてください。
親の話を聞くときは、無理に納得しようとしなくて大丈夫です。
わからないことや不安なことがあれば、遠慮せずに親に尋ねることも大切です。
- 感情を抑え込まない:
驚きや悲しみは自然な反応です。 - 疑問は素直に聞く:
不安や知りたいことは、そのまま親に伝えてみましょう。
自分のペースで受け止めていくことが、心の安定につながります。
無理にどちらかの味方をする必要はない
両親が離婚する際、「どちらの親についていくか」や「どちらかの味方にならなきゃいけないのかな」と悩むことがあります。
しかし、無理にどちらかを選んだり、片方だけを応援したりする必要はありません。
あなたは両方の親にとって大切な存在です。
離婚は大人同士の問題であり、子どもが責任を感じることではありません。
自分の気持ちに正直になり、「どちらも大切」「どちらとも離れたくない」と感じているなら、それをそのまま親に伝えても良いのです。
- 自分の気持ちを大切にする:
無理に役割を背負わなくても大丈夫です。 - どちらとも関係を続けることもできる:
離婚しても、両親と連絡を取り合うことはできます。
自分の選択や気持ちを責める必要はありません。
親にしてほしいこと・やめてほしいことの伝え方
親の離婚を経験すると、「こんなふうに接してほしい」「これはやめてほしい」と思うこともあるはずです。
例えば「自分の前で喧嘩しないでほしい」「無理に気持ちを聞き出そうとしないでほしい」など、具体的な要望があれば、それを伝えることも大切です。
伝え方のコツは、責めるのではなく「自分はこう感じている」と自分の気持ちを主語にすることです。
「私は、親が喧嘩していると悲しい」「急に予定が変わると不安になる」といった形で伝えると、親も気持ちを受け止めやすくなります。
- 自分の感情を率直に言葉にする:
「嫌だな」と感じた時は、勇気を出して伝えてみましょう。 - 伝えにくい時は、手紙やメモを使うのも有効:
言葉で伝えるのが難しい場合は、書いて伝える方法もあります。
あなたの気持ちや願いをきちんと伝えることで、親との関係がより良くなることがあります。
離婚後の親との連絡・面会交流について
離婚後、両親のどちらかと離れて暮らす場合、「もう会えなくなるのかな」「ちゃんと連絡を取れるのかな」と不安に思う方もいるでしょう。
実際は、離婚しても子どもが親と会ったり連絡を取ったりする「面会交流」という制度があります。
親と離れて暮らしても、定期的に連絡を取り合ったり、会いに行ったりすることができます。
面会の頻度や方法は、親同士の話し合いで決まりますが、「もっと会いたい」「もう少し連絡を取りたい」と感じた時は、自分の希望を親に伝えても構いません。
- 面会交流を利用する:
面会交流は子どもの権利です。
会いたい気持ちを大切にして良いのです。 - 連絡方法を決めておく:
電話やメール、ビデオ通話など、離れていてもつながる方法を相談しておくと安心です。
自分の気持ちを素直に伝えながら、両親とのつながりを保っていくことができます。

離婚後の生活の変化|お金・戸籍・相続のこと
親の離婚は子どもの毎日の暮らしや将来にも様々な変化をもたらします。
「お金のことや名字が変わるの?」「将来の相続や親の再婚相手とはどう付き合えばいいのかな」と不安や疑問を感じることもあるでしょう。
ここでは、離婚後に直面しやすい生活の変化について、子どもの視点で押さえておきたいポイントを解説します。
家計や進学の問題、戸籍や名字、万が一の相続や新しい家族との関係など、知っておくことで気持ちの準備がしやすくなります。
「こんなこと誰にも聞けない…」という悩みもあるかもしれませんが、まずは一つずつ事実を整理してみましょう。
以下で、よくある変化や注意点をわかりやすく説明します。
学費や養育費などお金の問題
離婚後は、親の収入が一方だけになる場合が多いため、家計に変化が生じます。
特に気になるのは「学費はどうなるの?」「お小遣いや生活費が減ってしまうのでは?」というお金の問題です。
離婚後の子どもの生活費や学費については、原則として子どもを育てていない側の親(非監護親)が「養育費」として毎月一定額を支払うことが法律で決められています。
養育費は子どもの生活や進学にとって大切な資金源です。
ただし、実際には支払いが滞るケースもあり、不安を抱える子どももいます。
そのため、何か困ったことがあれば、学校や相談窓口でサポートを受けられる仕組みがあります。
- 養育費の取り決め:
養育費は親同士の話し合いや、調停・公正証書などで取り決められます。 - 支払いが不安な場合:
市区町村の窓口や家庭裁判所、子ども家庭支援センターなどで相談ができます。
「学費はどうなるの?」という疑問は、具体的な制度やサポートを知ることで少しずつ不安を減らすことができます。


自分の戸籍や名字はどうなる?
親が離婚すると、子どもの戸籍や名字(姓)が変わる場合があります。
基本的に子どもは親権者となる親と同じ戸籍に入ることになります。
例えば、母親が親権者となった場合、子どもは母親の戸籍に移るのが一般的です。
また、親が旧姓に戻る場合、子どもも同じく名字が変わることがあります。
ただし、名字を変えたくない場合は、家庭裁判所に申し立てをすることで従来の名字を使い続けることも可能です。
- 戸籍の移動:
原則として親権者の戸籍に入ります。 - 名字の選択:
事情によっては旧姓を名乗ったり、そのままにしたり選ぶことができます。
名字や戸籍が変わる場合には手続きが必要なので、不明点があれば親や役所に相談しましょう。




片方の親が亡くなった場合の相続権
親が離婚しても、子どもは両親双方の法律上の子どもであり続けます。
そのため、親のどちらかが亡くなった場合、子どもには変わらず相続権があります。
「離婚したから相続できないのでは?」と心配する必要はありません。
ただし、親が再婚して新しい配偶者やその子どもができた場合、相続人の範囲や割合が変わることもあるため、不安な時は専門家に相談することも大切です。
親の再婚相手(新しい配偶者)との関係
離婚後に親が再婚するケースも珍しくありません。
新しい配偶者との関係については、「どうやって接したらいいの?」「今まで通りに親と話せるのかな」と不安を感じる方もいるでしょう。
新しい配偶者と子どもは、法律上は親子関係にはなりません。
ただし、養子縁組をした場合には法律上の親子となり、相続権も発生します。
無理に仲良くしようとしなくても、まずは自分のペースで距離を取ってよいのです。
- 再婚相手との関わり方:
無理をせず、ゆっくりと関係を築くことが大切です。 - 養子縁組がある場合:
法律上の親子関係が成立しますが、あなたの気持ちが最優先です。
どんな関係になったとしても、あなたの心を大切にして過ごしてください。

親の離婚に関するよくある質問
親の離婚については、実際に体験するまでは想像しにくい疑問や不安がたくさんあるものです。
「親権は誰が決めるの?」「離婚のことで弁護士に相談できる?」「再婚したらどうやって挨拶すればいい?」など、誰にも聞きづらいことも多いでしょう。
ここでは、子どもや若者からよく寄せられる質問に、専門家の立場からわかりやすく答えます。
一つ一つの疑問を解消することで、これからの生活や人間関係への不安を和らげる助けになります。
それぞれの質問について、具体的な答えを確認してみてください。
親権について子どもは意見を言える?
親権は原則として親同士の話し合いや家庭裁判所の判断で決まりますが、子どもの年齢や状況によっては、意見が尊重されることもあります。
特に10歳以上の子どもについては、裁判所が「どちらと暮らしたいか」を直接聞く場合があります。
- 意見表明権:
子どもが自分の気持ちや希望を伝える権利があります。 - 最終的な判断:
親や裁判所が子どもの利益を最優先にして決めます。
意見を伝えたい場合は、家庭裁判所や信頼できる大人に相談してみてください。
親の離婚で弁護士に相談は可能?
親の離婚に関して、不安や疑問があれば弁護士に相談することができます。
弁護士は親だけでなく、子どもの立場からも助言をしてくれる場合があります。
また、自治体や子ども家庭支援センターで無料相談を行っているところもあります。
- 無料相談窓口:
法テラスや自治体の相談会なども活用できます。 - 弁護士に相談するメリット:
法律的な仕組みや手続きの流れ、トラブルが起きた時の対応策を専門家から聞くことができます。
悩みを一人で抱え込まず、第三者の専門家を頼ることも選択肢の一つです。
離婚した親の相続放棄はできますか?
親が亡くなった時、相続を受けたくない場合は「相続放棄」という手続きをとることができます。
相続放棄は家庭裁判所に申立てることで可能です。
離婚して親と別々に暮らしていても、相続人としての権利や義務は残っていますが、自分の意思で相続しない選択もできます。
- 相続放棄の手続き:
親が亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所で申し立てます。 - 専門家に相談も可能:
手続きが分からない場合は、弁護士や司法書士に相談できます。
手続きを早めに行うことで、不要なトラブルを避けられます。
再婚相手との挨拶はどうすればいい?
親の再婚相手と初めて会う時は、「どう話したらいいんだろう」「何を言えば失礼にならないかな」と緊張する方も多いはずです。
無理に親しげに振る舞う必要はなく、まずは丁寧に挨拶することを心がけましょう。
- 自然体で丁寧に:
「はじめまして。これからよろしくお願いします」と短く伝えるだけで十分です。 - 自分のペースを大切に:
無理に打ち解けようとせず、少しずつ距離を縮めていきましょう。
最初は緊張して当たり前です。
焦らず、あなたらしいペースで関係を築いていけば大丈夫です。

まとめ:親の離婚を乗り越えるために大切なこと
この記事で、「親の離婚が子どもに与える影響」「辛い気持ちとの向き合い方」「離婚後の生活の変化」「よくある疑問や行動のヒント」などについて説明してきました。
親の離婚は、どんな年齢であっても心に大きな衝撃をもたらします。まず大切なのは、「自分の気持ちを認めること」「親の問題と自分の人生を切り離して考えること」「一人で抱え込まず、誰かに話すこと」です。この3つを意識するだけで、少しずつ心が軽くなり、自分の将来に向き合う勇気が湧いてくるはずです。「こんなことで悩んでいるのは自分だけかもしれない」と思いがちですが、同じ悩みを抱えている人は決して少なくありません。
今、迷いや不安を感じている方は、まず自分を責めず、心の声に耳を傾けてみてください。辛い気持ちや不安を無理に抑え込む必要はありません。もし一人で乗り越えられそうにないときは、信頼できる大人や、無料で相談できる窓口を活用してみましょう。あなたの抱える悩みは、必ず整理されていきます。
学費や生活費、親権や名字、親の再婚など現実的な課題に直面している場合や、「親の離婚で自分の進路や将来が変わるのでは」と不安なときは、専門家に相談することでより正確で早い解決策が見つかります。誰かに頼ることは、決して弱いことではありません。むしろ前に進むための大切な一歩です。
どんなに辛い状況でも、未来は必ず変えていけます。今は先が見えなくても、あなた自身の人生はあなたの選択で切り開けます。これからも自分の心を大切に、一歩ずつ歩みを進めていきましょう。
どんな小さな悩みでも、相談することをためらわず、少しずつ前向きな行動を積み重ねてください。あなたの未来を応援しています。

専門家に相談するなら「オンライン離婚相談 home」

男女関係や離婚の悩みって、
誰に相談したらいいんだろう…

弁護士やカウンセラーの事務所に
いきなり行くのはちょっと怖い…
\それなら…/
オンライン離婚相談 homeなら
来所不要、あなたのPC・スマホから
さまざまな専門家に相談できます。
夫婦関係や離婚に関する、あなたのお悩みに合った専門家とマッチング。いつでも好きなときにオンラインで相談できます。
夫婦関係の改善、離婚調停、モラハラ・DV、不倫・浮気、別居などさまざまなお悩みについて、専門家が寄り添います。匿名で利用できるため、プライバシーなどを気にせず、何でも安心してご相談いただけます。
24時間365日 オンライン相談できる

ビデオ通話、チャットからお好きな方法で相談いただけます。またプランも、1回ごとや月々定額(サブスク)からお選びいただけます。
厳選された専門家

弁護士、行政書士、探偵、離婚・夫婦問題カウンセラーなどの、経験豊富で厳選された専門家があなたの悩みに寄り添います。
離婚の公正証書が作成できる

離婚に強い女性行政書士に相談しながら、離婚条件を公正証書にすることができます。
公正証書にすることで、慰謝料や財産分与、養育費などが守られない場合、強制執行(給与、預貯金などの財産を差し押さえ)がカンタンになります。
養育費公正証書作成で数万円補助の可能性

養育費を取り決め、実際に受け取っているひとり親は、全体のわずか24.3%にとどまります。
この養育費未払い問題に、各自治体ではさまざまな支援制度が用意されています。
養育費に関する公正証書作成補助として、神奈川県は上限4万円、横浜市は上限3万円、川崎市は上限5万円などです(2025年4月時点)
参考:全国自治体の養育費支援、神奈川県の養育費支援

夫婦関係や離婚に関するお悩みを、24時間365⽇オンラインで解決できるオンライン離婚プラットフォーム。
夫婦関係の修復から、夫婦の話し合い、離婚相談、離婚後のサポートまで、専門家があなたの悩みに寄り添います。