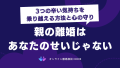「これから一人で子どもを育てていくなんて、経済的にやっていけるのかな…」
「誰にも相談できず、たった一人で未来と向き合っている気がする…」
離婚や未婚での出産を前に、こうした不安と孤独感で胸が張り裂けそうになっている方もいるでしょう。
その不安の多くは「知らないこと」から生まれます。
子どもとご自身の未来を守るためには、①使える制度を「知り」、②生活を「計画し」、③一人で抱え込まずに社会と「繋がる」ことが何よりも大切です。
あなたは決して一人ではありません。
今できることから、一つずつ準備を始めていきましょう。
この記事では、これからシングルマザーとして新しい人生を歩もうとしている方に向けて、主に以下を専門家視点でご説明します。
- プレシンママの時期に頼れる公的支援と制度
- 後悔しないための生活基盤(お金・仕事・住まい)の整え方
- 一人で悩まないための具体的な相談先リスト
未来が見えず不安でいっぱいかもしれませんが、大丈夫です。
この記事を読み終える頃には、漠然とした不安が「やるべきこと」に変わり、希望を持って次の一歩を踏み出せるようになっているはずです。


プレシンママとは?不安な時期を乗り越えるために
「プレシンママ」という言葉を目にしたあなたは今、子どもの未来とご自身の人生について、深く思い悩んでいるのかもしれません。
この言葉は、これからシングルマザーになる女性、つまり未来への不安と向き合う、とても大切な時期にいるあなたのためのものです。
「この先、子どもとどうやって生きていけばいいんだろう…」
そんな風に、たった一人で暗いトンネルの中にいるように感じている方もいるでしょう。
しかし、その不安の多くは「知らないこと」から生まれています。やるべきことを知り、一つずつ準備を進めることで、この期間は未来への希望に繋がる助走期間へと変わるはずです。
ここでは、プレシンママという言葉の意味と、この時期をどう過ごすべきかについて、詳しく解説していきます。
シングルマザーになる前の大切な準備期間
プレシンママとは、離婚や未婚での出産などを理由に、近い将来シングルマザーになることが見込まれる女性のことを指す言葉であり、新しい生活に向けての「大切な準備期間」です。
この期間の過ごし方が、あなたとお子さんのその後の人生を大きく左右すると言っても過言ではありません。お金のこと、仕事のこと、住まいのこと、そして法的な手続きなど、考えるべきことはたくさんあります。
もし、行き当たりばったりで行動してしまうと、受けられたはずの支援を受けられなかったり、本来主張できたはずの権利を失ってしまったりと、「あの時、もっと調べておけばよかった」と後悔することになりかねません。だからこそ、このプレシンママの時期に、計画的に準備を進めることが何よりも大切なのです。


離婚や未婚など、さまざまなケースが対象
プレシンママと一言でいっても、その背景にある事情は一人ひとり異なります。
この記事を読んでいるあなたも、様々な状況の中にいることでしょう。
例えば、以下のようなケースが考えられます。


なぜ今、準備と心の振り返りが必要なのか
後悔のない選択をし、お子さんとご自身の未来を守るためには、「実務的な準備」と「自分自身の心の振り返り」の両方が不可欠だからです。
まず、実務的な準備、つまりお金や手続きに関する知識は、新しい生活の土台となります。
国や自治体には、ひとり親家庭を支えるための多くの支援制度がありますが、そのほとんどは「申請」しなければ利用できません。知っているか知らないかで、受けられる支援に大きな差が生まれてしまうのです。
そして、それと同じくらい大切なのが、あなた自身の心を振り返る時間を持つこと。
不安や怒り、悲しみといった感情に飲み込まれたままでは、冷静な判断はできません。
一度立ち止まり、「自分は本当はどうしたいのか」「子どもにどんな人生を歩んでほしいのか」という心の軸を定めること。その軸こそが、これから訪れるであろう困難を乗り越えるための、一番の力になってくれるはずです。

まずは「知る」ことから。頼れる公的支援と制度
離婚後の生活、特にお金のことを考えると、目の前が真っ暗になるような気持ちになるかもしれません。
しかし、あなたが利用できる公的な支援制度がいくつもあることをご存知でしょうか。
これらの制度は、申請をしなければ利用できません。
知っているか知らないかで、離婚後の経済的な負担は大きく変わります。
ここでは、離婚した男性が利用できる可能性のある、主な公的支援や制度について解説します。
ご自身の状況と照らし合わせながら、確認してみてください。


①児童扶養手当:父子家庭も対象になる手当
「児童扶養手当」と聞くと、多くの方が母子家庭のための制度という印象を持つかもしれません。
しかし、この手当は、父子家庭であっても一定の条件を満たせば受給することが可能です。
これは、ひとり親家庭で育つ児童の福祉のために設けられた、大切な支援制度となります。
お子さんを養育していく上で、経済的な基盤の一つになるでしょう。
所得による制限など、受給にはいくつかの要件があります。
まずはお住まいの市区町村の窓口で、ご自身が対象となるか相談してみてはいかがでしょうか。
②医療費助成制度:子どもの医療費をサポート
お子さんの親権を持つことになった場合、急な病気や怪我の際の医療費は心配の種の一つでしょう。
そのような時に心強い味方となるのが、「ひとり親家庭等医療費助成制度」です。
この制度を利用すれば、病院などで支払う医療費の自己負担額が大幅に軽減されたり、自治体によっては無料になったりします。
お子さんが健やかに成長するための、非常に重要なサポートと言えるでしょう。
助成の内容や対象年齢は自治体によって異なります。
離婚の手続きが完了したら、速やかに役所の担当窓口で詳細を確認し、手続きを進めてください。
③国民年金・国民健康保険の免除・減額制度
離婚を機に退職したり、働き方が変わったりすると、厚生年金から国民年金へ、会社の健康保険から国民健康保険へと切り替える必要があります。
その際、毎月の保険料が大きな負担になることもあるでしょう。
もし経済的な理由で支払いが困難になったとしても、決して放置してはいけません。
失業や収入の減少といった事情に応じて、保険料の支払いが免除されたり、減額・猶予されたりする制度が存在します。
「払えないから」と諦めずに、必ず役所の担当窓口へ足を運び、正直に現在の状況を相談することが大切です。
④所得税・住民税の「ひとり親控除」
税金の負担を軽くするための制度も、ぜひ知っておきましょう。
以前は「寡夫(かふ)控除」という制度がありましたが、税制改正により、現在は「ひとり親控除」という、より利用しやすい制度に変わっています。
これは、婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じくする子がいるなどの要件を満たすひとり親が対象となる所得控除です。
年末調整や確定申告の際に申請することで、所得税や住民税の負担を軽減できます。
ご自身が対象になるかを確認し、忘れずに手続きを行うようにしてください。

次は「計画する」。生活基盤を整える3つの準備
利用できる制度を知った上で、次に行うべきは、新しい生活の土台を築くための具体的な「計画」を立てることです。
この計画こそが、漠然とした不安を「乗り越えるべき課題」へと変え、あなたに前に進む力を与えてくれます。
「本当に、私一人でやっていけるだろうか…」
経済的な不安は、心に重くのしかかるかもしれません。しかし、一つひとつ数字に落とし込み、やるべきことを具体化していくことで、進むべき道は必ず見えてきます。
ここでは、生活の根幹となる「お金」「仕事」「住まい」という3つの準備について、計画の立て方のポイントを解説します。
①お金の計画:養育費や生活費を把握する
まず不可欠なのが、現実的な収支計画を立てることです。
離婚後の収入と支出を具体的に書き出し、毎月の家計がどうなるのかを「見える化」しましょう。
収入の柱となるのは、ご自身の就労収入、児童扶y扶手当などの公的支援、そして子どもを育てるための「養育費」です。
養育費は、子どもの権利として、パートナーに必ず請求すべき大切なお金。
裁判所が公開する「養育費算定表」を参考に、相手の収入に応じた適正な金額を把握しておきましょう。
一方で、支出には家賃、食費、水道光熱費、通信費、子どもの教育費などがあります。
これらの具体的な金額を書き出すことで、毎月あといくら必要なのか、どのような働き方を目指すべきかという目標が明確になるはずです。
②仕事の計画:経済的自立に向けたキャリア
子育てと両立しながら安定した収入を得ることは、経済的な自立への最も重要なステップです。
ご自身の状況に合わせて、長期的な視点でキャリアプランを考えましょう。
すぐにでも働きたい、あるいは収入を増やしたいと考えている方には、以下のような選択肢があります。
- 資格を取得して専門職を目指す:
自治体が実施している「高等職業訓練促進給付金」などの制度を活用すれば、生活費の支援を受けながら看護師や保育士などの資格取得を目指すことも可能です。 - 子育てに理解のある職場で働く:
全国のハローワークに設置されている「マザーズコーナー」では、子育て中の女性を積極的に採用している企業の求人を紹介してくれます。 - 今あるスキルや経験を活かす:
事務職の経験があればリモートワーク可能な仕事を探すなど、ご自身の強みを活かせる道を探すのも一つの方法です。
すぐに収入を得ることと、数年後を見据えてスキルアップすること。両方の視点を持って、あなたに合った仕事の計画を立てていきましょう。
③住まいの計画:公営住宅や実家などの選択肢
子どもと安心して暮らせる住まいの確保は、生活の基盤を整える上で欠かせません。
経済的な状況や子どもの環境を考慮し、複数の選択肢を検討することが大切です。
主な選択肢として、以下が挙げられます。
- 公営住宅(都営・県営・市営住宅など):
所得に応じて安い家賃で入居できる住宅です。母子家庭などのひとり親世帯は、抽選時に優先される場合があるため、まずはお住まいの自治体の情報を確認してみましょう。 - 実家に戻る:
親のサポートを受けられることは、特に子どもが小さい場合に大きなメリットです。ただし、親子間のルールや精神的な距離感など、同居を始める前にしっかりと話し合う必要があります。 - UR賃貸住宅:
礼金・仲介手数料・更新料・保証人が不要な物件が多く、初期費用を大幅に抑えて転居できる可能性があります。
自治体によっては家賃補助制度を設けている場合もあります。諦めずに情報を集めることが、最適な住まいを見つける鍵となります。

一人で悩まず「繋がる」。頼れる相談先リスト
様々な制度を知り、計画を立てたとしても、その全てを一人で実行するのは大変なことです。
不安や困難に直面した時、専門家や支援機関と「繋がる」ことで、心は軽くなり、問題解決への道筋はより明確になります。
「こんなこと、誰に相談したらいいんだろう…」
そうやって一人で抱え込んでしまう必要は全くありません。専門家は、具体的な情報を提供してくれるだけでなく、あなたの気持ちに寄り添い、精神的な支えにもなってくれる存在です。
あなたの状況に応じて頼れる、具体的な相談先をいくつかご紹介します。
自治体の母子・父子自立支援員
まず最初に訪ねてほしいのが、お住まいの市区町村の役所に配置されている、ひとり親家庭専門の相談員です。
多くの場合、子育て支援課や福祉課などの窓口で相談できます。生活全般の悩みから、利用できる支援制度の案内、ハローワークや法的な相談窓口への紹介まで、ワンストップで対応してくれるのが特徴です。
もちろん相談は無料で、秘密は固く守られます。どこに相談していいか分からない時、最初の頼れる窓口となるでしょう。
ハローワークのマザーズコーナー
「仕事」に関する悩みや相談に特化した窓口が、ハローワークに設置されている「マザーズコーナー」です。
ここでは、子育てと両立しやすい求人の紹介はもちろん、応募書類の書き方や面接の対策、キャリアプランに関する相談まで、就職に関するあらゆるサポートを無料で受けられます。
キッズスペースが併設されていることも多く、お子さんと一緒でも安心して相談できる環境が整っている点も大きな魅力です。担当者制で継続的に支援してくれるため、心強いパートナーとなります。
NPO法人や民間の支援団体
公的な機関だけでなく、NPO法人や民間の団体も、ひとり親家庭に対して独自のきめ細やかなサポートを行っています。
例えば、企業や個人から寄付された食料を提供する「フードバンク」や、子どもたちの学習をサポートする学習支援、同じ境遇の親子が集う交流会の開催など、その活動は多岐にわたります。
公的支援ではカバーしきれない部分を支えてくれるだけでなく、「同じ悩みを持つ仲間と出会える」という精神的な繋がりは、何物にも代えがたい支えになるはずです。
「お住まいの地域名 ひとり親支援 NPO」などで検索してみてください。

離婚準備中の男性から寄せられる、よくある質問
離婚に向けて準備を進めていると、次から次へと疑問や不安が湧いてくるものです。
特に、これまで経験したことのない手続きやお金の問題については、多くの方が戸惑いを感じます。
ここでは、実際に離婚を考え始めた男性からよく寄せられる質問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。
Q. 離婚前でも手当は支給される?
A. 原則として、離婚成立後に申請・支給となります。
児童扶養手当など、ひとり親家庭を対象とした公的な手当の多くは、戸籍上「ひとり親」であることが確認されてから支給が開始されます。
そのため、離婚協議中や別居中といった段階では、基本的に対象となりません。
ただし、配偶者からのDV(ドメスティック・バイオレンス)が原因で避難しているなど、特別な事情がある場合は例外的に認められることもあります。
離婚が成立したら、速やかに役所の窓口で手続きを行いましょう。
Q. パートナーからの協力が得られない場合は?
A. 「婚姻費用」の請求を検討しましょう。
離婚が成立するまでの期間、夫婦は互いに生活を助け合う義務があります。
たとえ別居していても、収入の多い方が少ない方へ、生活費(婚姻費用)を支払うのが原則です。
相手が話し合いに応じず、生活費を渡してくれない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てることができます。
法的な手続きとなりますので、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
Q. 公営住宅の家賃割引などはありますか?
A. 優先的に入居できたり、家賃負担が軽くなったりする場合があります。
多くの自治体では、父子家庭を含むひとり親世帯を対象に、公営住宅への優先入居枠を設けています。
抽選の倍率が優遇されるなど、一般世帯よりも入居しやすくなる可能性があります。
また、公営住宅の家賃は、世帯の収入に応じて決まる仕組みです。
民間の賃貸物件に比べて、経済的な負担を大きく軽減できるケースも少なくありません。
募集の時期や条件は自治体によって異なるため、まずは住宅担当課へ問い合わせてみましょう。
Q. 支援を受けるための登録は必要?
A. 支援の種類によって異なります。
公的な手当や制度を利用するためには、役所への申請(登録)手続きが必ず必要です。
また、市区町村が実施している無料の法律相談なども、事前の予約が求められることがほとんどです。
一方で、どのような支援があるかを知るための情報収集や、NPO法人が運営する相談窓口の利用など、登録なしでアクセスできる支援もたくさんあります。
まずは気軽に相談できる窓口を探してみることから始めてはいかがでしょうか。
Q. 手当の支給金額は所得で変わる?
A. はい、所得によって大きく変わります。
例えば「児童扶養手当」は、申請者本人や同居している家族(扶養義務者)の所得に応じて、支給額が細かく決められています。
所得が一定額未満の場合は全額が支給されますが、それを超えると一部支給となり、さらに上限額を超えると支給が停止(対象外)となります。
所得制限の計算方法は少し複雑なため、ご自身のケースでいくら支給されるかを正確に知りたい場合は、お住まいの市区町村の担当窓口で確認するのが最も確実です。

まとめ:プレシンママの不安な時期は、未来への第一歩
この記事では、「プレシンママが利用できる支援制度」や「生活基盤を整えるための3つの準備」、「頼れる相談先」などについて解説してきました。
未来が見えず不安でいっぱいかもしれません。
しかし、利用できる制度を「知り」、具体的な生活を「計画し」、一人で悩まず誰かと「繋がる」ことで、その不安は乗り越えるべき課題へと変わるのです。
あなたとお子さんの未来を守る力は、あなた自身の中にあります。
まずは、この記事で紹介した中から、一つでも構いません。
今すぐできそうなことから行動に移してみましょう。
小さな一歩が、明日への大きな希望に繋がるはずです。
特に、「養育費や財産分与の取り決め」や「今後の生活設計への具体的な不安」については、専門家へ相談することで、より迅速かつ有利に解決できる可能性があります。
私たち「home」のようなプラットフォームには、あなたの状況に合わせた専門家が多数在籍しています。
今は先が見えない暗闇の中にいるように感じていることでしょう。
しかし、正しい知識と準備は、その暗闇を照らす確かな光となります。
子どもと笑顔で暮らす、穏やかな未来は必ずやってきます。
あなたは、決して一人ではありません。
自分の未来を、そして子どもの未来を、その手で掴み取るために。
さあ、勇気を出して、最初の小さな一歩を踏み出しましょう。

専門家に相談するなら「オンライン離婚相談 home」

男女関係や離婚の悩みって、
誰に相談したらいいんだろう…

弁護士やカウンセラーの事務所に
いきなり行くのはちょっと怖い…
\それなら…/
オンライン離婚相談 homeなら
来所不要、あなたのPC・スマホから
さまざまな専門家に相談できます。
夫婦関係や離婚に関する、あなたのお悩みに合った専門家とマッチング。いつでも好きなときにオンラインで相談できます。
夫婦関係の改善、離婚調停、モラハラ・DV、不倫・浮気、別居などさまざまなお悩みについて、専門家が寄り添います。匿名で利用できるため、プライバシーなどを気にせず、何でも安心してご相談いただけます。
24時間365日 オンライン相談できる

ビデオ通話、チャットからお好きな方法で相談いただけます。またプランも、1回ごとや月々定額(サブスク)からお選びいただけます。
厳選された専門家

弁護士、行政書士、探偵、離婚・夫婦問題カウンセラーなどの、経験豊富で厳選された専門家があなたの悩みに寄り添います。
離婚の公正証書が作成できる

離婚に強い女性行政書士に相談しながら、離婚条件を公正証書にすることができます。
公正証書にすることで、慰謝料や財産分与、養育費などが守られない場合、強制執行(給与、預貯金などの財産を差し押さえ)がカンタンになります。
養育費公正証書作成で数万円補助の可能性

養育費を取り決め、実際に受け取っているひとり親は、全体のわずか24.3%にとどまります。
この養育費未払い問題に、各自治体ではさまざまな支援制度が用意されています。
養育費に関する公正証書作成補助として、神奈川県は上限4万円、横浜市は上限3万円、川崎市は上限5万円などです(2025年4月時点)
参考:全国自治体の養育費支援、神奈川県の養育費支援

夫婦関係や離婚に関するお悩みを、24時間365⽇オンラインで解決できるオンライン離婚プラットフォーム。
夫婦関係の修復から、夫婦の話し合い、離婚相談、離婚後のサポートまで、専門家があなたの悩みに寄り添います。