「最近わけもなくイライラするし、自分は父親失格なんじゃないか…」
「笑顔が消えた夫。どう接すればいいのか分からず、不安でたまらない…」
産後のパパの心身の変化に、ご自身やパートナーが戸惑い、深く悩んでいる方もいるでしょう。
パタニティブルーは、決して個人の気の持ちようや覚悟の問題ではありません。
それは産後の急激な環境変化がもたらす、夫婦共通の課題なのです。
そして、この産後のすれ違いを放置してしまうことが、時として深刻な夫婦の危機につながるケースを、専門家として数多く見てきました。
だからこそ、一人で抱え込まず、まずはこの問題について正しく知ることが、解決への最も大切な第一歩となります。
この記事では、産後のパパご自身の不調に悩んでいる方や、パートナーの変化に戸惑っている方に向けて、主に以下を専門家の視点でご説明します。
- パタニティブルーの具体的な症状や原因
- 夫婦で乗り越えるための対処法と体験談
- 妊娠中からできる効果的な予防策
この記事を読めば、漠然とした不安の正体がわかり、明日から何をすべきかが見えてくるはずです。
どうか一人で悩まないでください。
ぜひ最後までお読みいただき、ご自身の状況を改善するヒントにしてください。


パタニティブルーとは?まじめな男性ほどなりやすいって本当?
「父親になるんだから、しっかりしなきゃいけないのに…」
「妻の方が大変なはずなのに、自分が落ち込んでいるなんて情けない」
そんな風に、誰にも言えずに一人で抱え込んでいませんか。
実は、パタニティブルーは、「良い父親にならなければ」というプレッシャーを感じやすい、責任感が強く、真面目な男性ほど陥りやすいと言われています。
パタニティブルーとは、父親が育児に参加する中で、睡眠不足や気分の落ち込み、イライラなどの精神的な不調を経験する状態を指します。
マタニティブルーと同様に、子育てにおける変化やストレスが原因で起こることがあります。
以下で、パタニティブルーの実態や、ママの産後うつとの違い、そして放置した場合のリスクについて詳しく解説していきます。
父親の約10人に1人が経験する産後の心の不調
パタニティブルーは、決して特別なことではなく、統計的にも父親の約10%が経験すると言われています。これは「産後うつ」と診断される母親の割合とほぼ同じ水準であり、父親にとっても産後は、人生における大きな心身の変化の時期なのです。
なぜ、直接出産を経験しない父親も、心身の不調に陥ってしまうのでしょうか。その原因は、主に以下の点にあると考えられています。
パタニティブルーの主な症状
これらの要因が複雑に絡み合い、イライラしやすくなる、仕事に集中できない、お酒の量が増える、育児に関わるのが億劫になる、といった症状として現れるのです。
ママの産後うつとの違いと共通点
パタニティブルーは、ママが経験するマタニティブルーや産後うつと、症状やその辛さにおいて共通する部分が多いですが、その背景や表面的な現れ方に違いが見られます。
【共通点】
気分の落ち込み、不安感、イライラ、不眠といった睡眠障害、これまで楽しめていた趣味への興味の喪失など、うつ的な症状が現れる点は共通しています。また、その根本的な原因として、生活の激変や睡眠不足、将来への漠然とした不安などが挙げられる点も同じです。
【相違点】


放置すると離婚の危機にもつながる「夫婦の問題」
パタニティブルーを「父親個人の気合の問題」として放置してしまうと、夫婦関係の悪化を招き、最悪の場合「産後クライシス」からの離婚につながるという、深刻なリスクをはらんでいます。
パタニティブルーに陥った夫は、プレッシャーと孤独感からイライラし、育児に非協力的な態度をとったり、妻に心ない言葉をぶつけたりしがちです。一方で、産後の妻も心身ともに限界の状態。夫の非協力的な態度に深く傷つき、「この人は、父親としても、夫としても、もうパートナーではない」という絶望感を募らせます。
こうして夫婦の会話は途絶え、お互いへの不信感だけが募っていきます。夫は家庭に居場所を感じなくなり、さらに仕事や飲み会に逃避する。妻はワンオペ育児で心身ともに追い詰められていく。この負のループが、夫婦の絆を完全に破壊してしまうのです。
パタニティブルーは、夫だけの問題ではありません。それは、産後の夫婦がチームとして乗り越えるべき「共通の課題」です。夫の精神的な不調は、妻や子どもへの虐待のリスクを高めるという研究結果もあり、決して軽視できません。早期に夫婦で問題を共有し、「私たち、ちょっと今、大変な時期だね」と認め合い、協力して対処することが、家族全員の幸せを守ることに繋がるのです。




これってパタニティブルー?夫の症状セルフチェックリスト
パタニティブルーの症状は、気分の落ち込みだけでなく、これまでになかった行動の変化や、身体の不調としても現れます。「父親なんだからしっかりしろ」と、ご自身の心や体の変化を見過ごしていませんか。
「最近、どうもイライラしやすいな…」
「仕事のミスが増えたのは、単なる疲れのせいだろうか…」
それは、あなたの性格や能力の問題ではなく、パタニティブルーという、産後の父親が経験する特有の心身の不調が原因かもしれません。まずはご自身の状態を客観的に把握することが、回復への第一歩です。
以下に挙げる代表的な症状に、ご自身が当てはまらないかチェックしてみてください。これは医学的な診断ではありませんが、自分を理解するための一つの手がかりとなります。
理由もなくイライラ、不安になる
これまでは気にならなかったような些細なことで、急にカッとしたり、あるいは漠然とした不安に襲われたりするのは、パタニティブルーの代表的な精神症状です。
例えば、思い通りにならない育児や、赤ちゃんの泣き声に対して、自分でも驚くほど強いイライラを感じてしまう。あるいは、妻の何気ない一言に過剰に反応し、腹を立ててしまう。
その一方で、「ちゃんと家族を養っていけるだろうか」「良い父親になれるのだろうか」といった将来への不安が常に頭から離れず、心が休まらない状態が続くこともあります。
これらの感情の起伏は、父親になったことへのプレッシャーや、急激な環境の変化によるストレスが、あなたの感情をコントロールする機能を低下させているために起こります。決して、あなたの性格が悪くなったわけでも、心が狭くなったわけでもないのです。
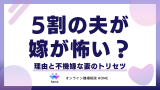
とは?3つの原因と対処法を専門家が解説【完全版】-160x90.png)

今まで好きだったことが楽しめない
以前はあれほど熱中していた趣味や、週末の楽しみだった友人との集まりなどに、全く興味が湧かなくなり、心から楽しめなくなるのも、注意すべきサインです。
これは、心理学で「アンヘドニア(快感消失)」と呼ばれる、うつ病にも見られる中核的な症状の一つです。
もし、このような状態に心当たりがあるなら、それは心のエネルギーが、育児へのプレッシャーや環境の変化に対応することで使い果たされ、楽しみを感じる余裕がなくなってしまっている証拠です。心が「もう限界だ、休ませてくれ」と悲鳴を上げているサインと受け止める必要があります。


仕事や育児に集中できない
仕事中に子どものことが気になって集中できなかったり、逆に家にいても仕事のことばかり考えて育児に身が入らなかったりするなど、思考がまとまらず、目の前のことに集中できなくなるのも特徴的な症状です。
常に頭の中に「ミルクの時間は大丈夫か」「今日の仕事の納期は…」「妻は機嫌が悪くないか」といった、様々な心配事が浮かんでいるため、脳が休まる暇もなく、注意力が散漫になってしまいます。
その結果、以下のようなことが増えるかもしれません。
これは、あなたの能力ややる気が低下したわけではありません。環境の急激な変化や、増大した責任によって、脳の情報処理能力が一時的に追いつかなくなっている状態なのです。
眠れない、または寝すぎてしまう
夜、布団に入ってもなかなか寝付けなかったり、夜中に何度も目が覚めたりする「不眠」、あるいは、休日にいくら寝ても眠気が取れず、一日中だるい「過眠」といった、睡眠に関する問題も代表的な身体症状です。
特に不眠は、赤ちゃんの夜泣きによる物理的な中断だけでなく、心理的な要因も大きく関わっています。日中のプレッシャーや将来への不安によって、心身の興奮を司る交感神経が高ぶったままになり、リラックスして深い眠りに入ることができないのです。
一方で過眠は、精神的なストレスや現実から逃避するために、体が過剰な睡眠を求めている状態とも考えられます。
睡眠の質の低下は、日中のイライラや集中力不足に直結し、症状をさらに悪化させるという悪循環を生みます。単なる「育児による寝不足」と軽視せず、心身の不調の重要なサインとして捉えることが大切です。

パタニティブルーに陥る主な3つの原因
パタニティブルーは、決して「気合が足りない」「父親としての自覚がない」といった精神論の問題ではありません。父親になった男性を取り巻く、心理的・社会的・そして身体的な要因が複雑に絡み合って引き起こされるのです。
その原因を正しく理解することは、ご自身を「ダメな父親だ」と責めることから解放され、適切な対処法を見つけるために不可欠です。
以下で、パタニティブルーに陥る主な3つの原因について、詳しく見ていきましょう。
①育児と仕事の両立によるプレッシャー
現代の父親には、「仕事で成果を出し、家計を支える」という伝統的な役割と、「家庭で育児に積極的に関わる」という新しい役割の、二つが同時に求められます。この両立へのプレッシャーが、非常に大きなストレス源となります。
「男は仕事」という旧来の価値観と、「育児は夫婦で協力して当たり前」という新しい時代の価値観の板挟みになり、「完璧な父親にも、完璧な社会人にもならなければ」と、無意識のうちに自分自身を追い込んでしまうのです。
特に、男性の育児休業取得がまだ十分に浸透していない職場では、育休取得や時短勤務に対する風当たりが強く、キャリアへの不安を感じることも少なくありません。また、残業が減ることで収入が減少し、増大した家族の生活費をまかなえるのか、という現実的な経済的プレッシャーも、心を重くさせます。


②夫婦の時間が減ることによる孤独感
子どもが生まれると、夫婦の関係性は「恋人」から「育児を共にするチーム」へと大きく変化します。この変化にうまく適応できず、妻との関係における「疎外感」や「孤独感」が、パタニティブルーの大きな引き金になることは非常に多いです。
これまで自分に向けられていた妻の関心は、そのすべてが赤ちゃんに注がれます。二人きりでゆっくり話す時間は激減し、妻は常に赤ちゃんの世話か、自身の体の回復で手一杯。身体的な触れ合いも当然のように減っていきます。
その結果、「自分はもう夫として愛されていないのではないか」「この家で、自分だけが孤立している」といった、深い寂しさを感じてしまうのです。この寂しさや不安を、疲れている妻に打ち明けることもできず、また「男がそんなことで悩むな」というプライドから、誰にも相談できずに一人で抱え込んでしまうことが、症状をさらに深刻化させます。




③ホルモンバランスの変化や睡眠不足
心理的な要因だけでなく、男性自身の「ホルモンバランスの変化」や、慢性的な「睡眠不足」といった、身体的な要因も大きく関わっています。
意外に思われるかもしれませんが、父親になることで男性のホルモンバランスも変化することが、近年の研究で示されています。愛情ホルモンとも呼ばれる「オキシトシン」や、母性を高める「プロラクチン」などが増加する一方で、競争心や攻撃性に関わる男性ホルモン「テストステロン」が減少することが報告されているのです。このホルモンの変動が、情緒の不安定や気分の落ち込みに、少なからず影響を与えている可能性があります。
そして何より深刻なのが、睡眠不足の影響です。
赤ちゃんの夜泣きや、早朝の授乳などで、まとまった睡眠が取れない状態が続くと、脳は正常な思考力や判断力を失い、うつ病のリスクが飛躍的に高まります。これは、精神論ではどうにもならない、純粋な身体的・生理的な問題なのです。

【体験談】私たちはこうして産後の危機を乗り越えました
パタニティブルーや産後のすれ違いは、夫婦にとって大きな危機ですが、それを乗り越え、以前よりも強い絆で結ばれた夫婦もたくさんいます。
今は先の見えない暗いトンネルの中にいるように感じられるかもしれません。しかし、他の夫婦がどのようにして光を見出し、危機を乗り越えたのか。そのリアルな体験談を知ることは、あなたにとって大きな希望と、具体的な行動のヒントになるはずです。
ここでは、実際に産後の危機を乗り越えた3組の夫婦の「体験談」をご紹介します。
CASE1:お互いの不安をとことん話し合った夫婦
妻の「産後のイライラ」と、夫の「父親としてのプレッシャー」が衝突し、会話のない冷戦状態に陥ってしまった夫婦が、一晩かけてお互いの不安を正直にぶつけ合うことで、関係を修復したケースです。
子どもが生まれて3ヶ月。妻のAさんは、24時間続く育児と睡眠不足で、常にイライラしていました。一方、夫のBさんは、昇進したばかりの仕事のプレッシャーと、「一家を支えなければ」という重圧で、家に帰っても無口になるばかり。Aさんには、そんなBさんの態度が「育児に無関心」としか映らず、二人の溝は深まる一方でした。
ある夜、赤ちゃんの夜泣きをきっかけに、ついにAさんの不満が爆発。「もう限界。あなたの考えていることが、何も分からない!」と、涙ながらに訴えました。その言葉をきっかけに、Bさんも初めて自分の胸の内を明かします。「父親失格だと思われたくなくて、会社で辛いことがあっても、疲れていても、弱音を吐けなかった。どうしていいか分からなかったんだ」と。
妻は「自分だけが辛い」と思い込み、夫は「夫として、父親として強くあらねば」と自分を追い込んでいた。お互いが、全く違う方向を向いて、一人で戦っていたことに気づいたのです。
その夜、二人は具体的な解決策を見つけたわけではありません。しかし、「ただ、お互いの不安や弱さを、評価も否定もせずに聞き合う」という時間を過ごしたことで、張り詰めていた心の糸がほぐれ、再び相手を思いやる気持ちを取り戻すことができました。この対話が、二人が本当の意味で「育児チーム」になるための、最初の、そして最も重要な一歩となったのです。
CASE2:「夫が一人になる時間」を意識して作った妻
夫が趣味の時間を全く取れなくなり、明らかに元気をなくしてしまった状況を察した妻が、意識的に「夫を一人にする時間」を作ることで、夫のパタニティブルーを解消したケースです。
Cさん夫婦は、待望の第一子を授かり、夫のDさんも積極的に育児に参加していました。しかし、産後数ヶ月が経った頃から、Dさんは明らかに口数が減り、家にいてもため息ばかりつくように。あれほど好きだったオンラインゲームも全くしなくなり、休日はただぼーっとテレビを見て過ごすだけ。その様子に、妻のCさんは「もしかして、父親になったことが負担なのかな」と不安を感じていました。
ある日、CさんはDさんに、「最近、元気ないね。たまには昔みたいに、夜に友達とゲームでもしてきたら?赤ちゃんは私が見てるから大丈夫だよ」と、思い切って声をかけました。Dさんは最初、「いや、大丈夫だよ」と遠慮していましたが、Cさんが「あなたが元気でいてくれる方が、私にとっては助かるから」と伝えると、少し申し訳なさそうに、ゲームをするために部屋にこもりました。
数時間後、Dさんの表情は、ここ数ヶ月見たことがないほど、晴れやかでした。自分の時間を持ち、リフレッシュできたことで、心に余裕が生まれたのです。
それ以降、Cさんは週に一度、数時間でもDさんが一人になれる時間を作るように心がけました。その結果、Dさんは以前の明るさを取り戻し、より積極的に育児に関わるようになり、妻への感謝の言葉も自然と増えていきました。「パパにも、息抜きという名の充電時間が必要なんだ」という妻の深い理解と配慮が、家庭全体の雰囲気を劇的に好転させたのです。
CASE3:育児の役割分担を一度リセットした夫婦
「俺だって手伝っている」という夫と、「私のやっていることの、ほんの一部でしょ!」という妻の不満が爆発した夫婦が、第三者(市の保健師)のアドバイスで、育児の役割分担を「見える化」し、リセットしたケースです。
共働きで1歳の子どもを育てるEさん夫婦。夫のFさんは、「平日のゴミ出しと、週末のお風呂掃除は俺の担当だ。自分は育児に協力的な夫だ」と思っていました。しかし、妻のEさんは、食事の準備、洗濯、掃除、保育園の送迎、寝かしつけといった「名もなき家事・育児」の膨大な量に、心身ともに疲れ果てていました。
ある日、「もっと主体的にやってよ!」というEさんの言葉に、Fさんが「俺だってやってるだろ!」と反論し、大喧嘩に。関係修復の糸口が見えない中、Eさんは乳幼児健診で市の保健師に、思い切って悩みを相談しました。そこで保健師さんから、「一度、全ての家事・育児タスクを書き出して、どちらがやっているか、客観的に見てみては?」とアドバイスを受けました。
その夜、二人は紙とペンを用意し、「授乳」「おむつ替え」「寝かしつけ」「沐浴」「離乳食作り」「着替え」「爪切り」「保育園の連絡帳記入」「洗濯(洗う・干す・畳む)」「食事作り(朝・昼・晩)」「食器洗い」…考えられる全てのタスクを書き出しました。そして、どちらが主に担当しているかに色分けをしていきました。
結果は一目瞭然。紙は、妻のEさんの色でほとんどが埋め尽くされていました。Fさんは、自分が担当していた家事が、育児全体のタスクの中で、いかにごく一部であったかを初めて視覚的に理解し、愕然としました。「ごめん、こんなに大変だったなんて、全然分かっていなかった」と。
この「見える化」をきっかけに、二人は冷静に役割分担を見直しました。「夜間のミルクは自分が担当する」「保育園の送りは自分が行く」など、夫が具体的な担当を決めたことで、妻の負担は軽減され、夫への不満も解消されていきました。

【専門家が解説】夫婦で乗り越えるための具体的な対処法3選
産後の夫婦の危機は、特別なことではなく、多くの夫婦が通る道です。感情的になりがちなこの時期だからこそ、客観的で具体的な対処法を知っておくことが、冷静さを取り戻し、夫婦関係の破綻を防ぐための羅針盤となります。
専門家の視点から見ても、この危機を乗り越えるために最も重要なポイントは、3つに集約されます。
以下で、多くの夫婦をサポートしてきた専門家として、すぐに実践できる3つの対処法を厳選して解説します。
まずはお互いの状況を否定せず共有する
最も重要で、かつ全ての基本となる最初のステップは、お互いの「辛さ」や「不安」を、評価や否定をせずに、ただ言葉にして共有することです。
産後の夫婦は、お互いに見えない鎧をまとっています。
妻は、「赤ちゃんは可愛いのに、涙が出てしまう自分は母親失格だ」という罪悪感と孤独感。
夫は、「一家の大黒柱として、父親として、弱音は吐けない」というプレッシャーと疎外感。
お互いが、相手に心配をかけまい、あるいは失望させまいとして、本当の気持ちを隠してしまいがちです。
まずは、どちらからでも構いません。勇気を出して、自分の弱さを開示してみましょう。
「最近、なんだか分からないけど、すごく不安なんだ」
「俺も、父親としてのプレッシャーで、正直いっぱいいっぱいだ」
大切なのは、相手の言葉に対して「そんなことで?」と否定しないこと。「そうか、君も辛かったんだね」「あなたも、大変だったんだね」と、ただ受け止める。
この「自己開示」と「受容」のキャッチボールこそが、孤立した二人を再び繋ぎ合わせ、夫婦というチームを再結成させるための、最も重要な信頼回復のプロセスなのです。
「完璧な育児」という理想を捨てる
夫婦二人で、「100点満点の親になろう」という、知らず知らずのうちに抱いてしまっている高い理想を、思い切って捨てることが、心の余裕を生み出します。
特に、現代はSNSなどを通じて、他の家庭の「キラキラした育児」が目に入りやすい時代です。きれいに片付いた部屋、手の込んだキャラクター離乳食、いつもニコニコ笑顔の親子。それらを見て、「それに比べて、うちはなんてダメなんだろう」と、無意識に自分たちを追い詰めてしまっていませんか。
しかし、SNSで見えるのは、誰かの人生の「一番良い瞬間」を切り取った、ほんの一部分に過ぎません。現実の育児は、もっと泥臭く、思い通りにいかないことの連続です。
「今日の夕飯は、レトルトカレーと納豆ごはんで済ませよう」
「部屋が散らかっていても、誰も死にはしない」
「赤ちゃんが泣き止まないときは、夫婦で交代しながら抱っこして、一緒に途方に暮れよう」
それで良いのです。夫婦で「手抜き育児」「頑張りすぎない育児」をスローガンに掲げ、お互いを追い詰めない環境を作りましょう。完璧ではない自分たちを、夫婦で笑い飛ばせるようになったとき、家庭は本当の意味で安らげる場所になります。
専門家や公的な相談窓口を頼る
「夫婦の問題は、夫婦だけで解決しなければならない」という考えは、産後においては、最も危険な思い込みの一つです。積極的に、第三者の力を借りてください。
産後の夫婦をサポートするための、専門家や公的なサービスは、あなたが思っている以上にたくさん存在します。これらを頼ることは、決して恥ずかしいことでも、特別なことでもありません。むしろ、情報を知り、賢く活用することこそが、現代の親に求められるスキルといえます。
外部のサポートを得て、親が少しでも休息を取り、心に余裕を持つこと。それが、家庭内に笑顔を取り戻すための、最も確実で賢明な方法なのです。







妊娠中から夫婦でできるパタニティブルーの予防対策
パタニティブルーは、産後いきなり始まるわけではありません。妊娠中からの夫婦のコミュニケーションと、具体的な準備が、発症を予防し、たとえ発症しても軽度で乗り切るための最大の鍵となります。
産後の生活は、夫婦がこれまで経験したことのない、未知の領域です。その変化を「想定内」のものにするための準備が、心に余裕を生み、夫が感じるプレッシャーや孤独感を和らげるのです。
以下で、妊娠中から夫婦で一緒に取り組める、3つの具体的な予防対策について解説します。
産後の生活や役割分担をイメージしておく
妊娠中のうちから、産後の生活がどのように変化するのかを夫婦で具体的に話し合い、役割分担をイメージしておくことが非常に重要です。
まずは、育児雑誌やウェブサイト、自治体や産院が開催する両親学級などを活用し、「産後1ヶ月のリアルな生活」について夫婦で一緒に学びましょう。「赤ちゃんは3時間おきに起きるらしい」「産後のママの体は交通事故レベルのダメージを受けているらしい」といった基本的な知識があるだけでも、産後の現実に対する心構えが全く違ってきます。
その上で、以下のような具体的な役割分担を、今のうちから話し合っておくことをお勧めします。
- 夜間の対応:
夜中の授乳やおむつ替えは、どのように分担するか?(例:夫は週末の夜間を担当する、ミルクの時間は夫が担当する、など) - 家事の分担:
食事の準備、洗濯、掃除、買い物。産後1ヶ月は、誰がどのように担当するのか?(例:平日の夕食は夫が買って帰る、週末に夫が作り置きをする、など) - 手続き関連:
出生届や児童手当の申請など、産後に必要な役所への手続きは、どちらが担当するか?
この時点で、すべてを完璧に決める必要はありません。大切なのは、「産後は、これまで通りにはいかない」「二人で協力しなければ乗り切れない」という共通の認識を夫婦間で持っておくことです。この事前のすり合わせが、産後の「こんなはずじゃなかった」というすれ違いを防ぐ、最大の予防策になります。


お互いの息抜きの時間を確保する方法を決める
産後の生活では、夫婦それぞれの「一人の時間」を意図的に確保することが、精神的な健康を保つ上で不可欠です。そのためのルールを、妊娠中から夫婦で話し合っておきましょう。
産後は、24時間365日、赤ちゃん中心の生活となり、自分の時間は文字通り皆無になります。これが、パタニティブルーやマタニティブルーの大きな引き金となります。「父親になったんだから」「母親になったんだから」と、自分の時間を犠牲にすることを当たり前だと思ってはいけません。
以下のようなルールを、妊娠中に二人で合意しておくことをお勧めします。
これは、遊びやサボりの時間ではありません。それは、親としての役割を長く、そして健康に続けていくための、心と体をメンテナンスするための重要な時間なのです。「自分だけが休んで申し訳ない」という罪悪感をお互いに持たず、「お互い様」の精神で、お互いの自由時間を尊重し合うという合意を形成しておくことが、産後の心の健康を守ります。
頼れる人や外部サービスをリストアップする
「育児は、夫婦二人だけで乗り切れるものではない」という前提に立ち、妊娠中から、いざという時に頼れる人や外部サービスをリストアップし、「見える化」しておきましょう。
産後は、心身ともに余裕がなく、誰かに助けを求めることすら困難になります。スマートフォンの連絡先に入っているだけでは不十分です。冷蔵庫に貼っておくなど、夫婦でいつでも確認できる「お助けリスト」を事前に作成しておくことが、産後の夫婦を救う命綱となります。
【お助けリストの作成例】
- 親族・友人:
双方の両親や兄弟姉妹、近所に住む友人など。具体的に「誰に」「何を」お願いできそうかを話し合っておく。(例:義母には週2回の夕食の差し入れ、実母には週末の沐浴の手伝い、など) - 公的サービス:
お住まいの自治体の保健センターの連絡先、産後ケア事業のパンフレット、ファミリー・サポート・センターの登録方法、一時保育の利用案内など。 - 民間サービス:
ベビーシッター、家事代行サービス、ネットスーパー、食事の宅配サービス(ヨシケイ、Oisixなど)の連絡先やウェブサイト。
このリストがあるだけで、「いざとなったら、これを使えばいい」という心のセーフティネットになり、夫婦が抱える精神的な負担を大きく軽減することができます。

パタニティブルーに関するよくある質問
父親の産後の不調であるパタニティブルーは、まだ社会的な認知が十分とは言えず、多くの疑問や不安が寄せられます。
一人で悩まず、正しい知識を持つことが、あなたと、そして大切な家族を守るための第一歩です。
ここでは、パタニティブルーに関する特によくある3つの質問にお答えします。
Q. 病院に行くなら何科?クリニックの選び方は?
イライラや気分の落ち込み、不眠といった精神症状が強く、日常生活に支障が出ている場合は、「心療内科」または「精神科」の受診が基本となります。
精神科や心療内科の受診に、抵抗やためらいを感じる方もいるかもしれません。しかし、これらは「心の風邪」を診てくれる専門家であり、客観的な視点からあなたの状況を整理し、回復への手助けをしてくれます。必要に応じて、気持ちを安定させる薬を処方してもらうこともできます。
クリニックを選ぶ際は、以下のような点を参考にすると良いでしょう。
- ウェブサイトなどで、医師の専門分野を確認する:
「男性のうつ」や「職場のメンタルヘルス」などに詳しい医師であれば、よりあなたの状況を理解してくれる可能性が高いです。 - 会社の産業医や、自治体の相談窓口を利用する:
いきなりクリニックを探すのが難しい場合は、まず会社の産業医(いる場合)や、お住まいの市区町村が設けている「精神保健福祉センター」などの相談窓口に連絡し、適切な医療機関を紹介してもらうのも良い方法です。
Q. 自分ですぐにできるセルフケアはありますか?
はい、あります。専門家への相談と並行して、日々の生活の中で意識的にセルフケアを取り入れることが、症状の悪化を防ぎ、回復を早める助けとなります。
- 短時間でも体を動かす:
15分程度のウォーキングやストレッチでも、気分転換に大きな効果があります。体を動かすことで、幸せホルモン「セロトニン」の分泌が促されます。 - 一人になれる時間を確保する:
たとえ通勤中の電車内での10分間でも構いません。好きな音楽を聴いたり、目を閉じて深呼吸したり、意識的に仕事や育児から離れ、自分の世界に没頭する時間を作りましょう。 - 信頼できる人に話す:
妻に話すのが難しければ、学生時代の友人や、同じように子どもを持つ同僚に、「最近、父親になったプレッシャーで少し疲れているんだ」と、正直に話してみましょう。言葉にするだけで、気持ちは楽になります。 - 完璧な父親を目指さない:
「100点満点の父親なんていない」と、自分自身への高いハードルを下げてあげてください。「できないことがあっても当然」と、不完全な自分を許してあげることが、何よりのセルフケアです。
Q. 妻も辛い時、一緒にどう乗り越えればいいですか?
産後は、夫婦が二人とも心身の危機に陥りやすい、人生で最も過酷な時期と言っても過言ではありません。この危機を乗り越える鍵は、「完璧な父母を目指す」のではなく、「不完全な戦友として、お互いを労い合う」ことです。
妻もマタニティブルーで辛い状況にあることを理解し、お互いの不調を「お前のせいだ」と責め合うのではなく、「共通の課題」として捉え直しましょう。夫が自分の辛さを打ち明けることは、妻に「私だけじゃなかったんだ」という安心感を与えることにも繋がります。
【具体的なアクション例】
- 感謝と労いの言葉を伝える:
「俺も辛いけど、君はもっと大変だよね。いつも本当にありがとう」と、妻の頑張りを具体的に認め、感謝の言葉を伝える。 - 育児のレベルを、夫婦で意図的に下げる:
「今日の夕食は、二人とも疲れているから、出前で済ませよう」「部屋が散らかっていても、今は気にしないでおこう」と、夫婦で合意の上で「手抜き」をする。 - 一緒に外部のサポートを頼る:
夫婦で一緒に、地域の保健師さんに相談に行ったり、産後ケアサービスについて調べたりする。
夫婦が「完璧な父母チーム」を目指すのではなく、「お互いをいたわり合いながら、今日一日を何とか生き延びる生存チーム」になること。この視点の転換が、産後の危機を乗り越える最大の力となります。

まとめ:パタニティブルーは夫婦で乗り越える最初の壁です
この記事で、「パタニティブルーの具体的な症状や原因」「夫婦でできる対処法や予防策」などについて説明してきました。
パタニティブルーは、決して父親一人の問題ではなく、夫婦が「チーム」として向き合うべき共通の課題です。
なぜなら、個人の心の弱さが原因なのではなく、産後の急激な環境変化が引き起こすものだからでしょう。
「父親失格だ」と自分を責めたり、「どうして私だけ」とパートナーに不満を感じたり、一人で抱え込んでしまうそのお気持ち、痛いほどわかります。
まずはこの記事で紹介した対処法、特に「お互いの状況を否定せず共有する」ことから始めてみませんか。
たったそれだけのことが、固く閉ざされた心の扉を開く、最初の鍵になるかもしれません。
それでも夫婦のすれ違いが埋まらない、関係の悪化が怖いといった悩みについては、専門家へ相談することでより迅速かつ円満に解決できる可能性があります。
私たちのような夫婦問題の専門家は、客観的な視点であなたの状況を整理し、最適な次の一歩を見つけるお手伝いができます。
この産後の危機は、乗り越え方次第で、お二人の絆を以前よりも遥かに強く、そして深いものへと変える絶好の機会にもなり得るのです。
雨降って地固まる、という言葉もあります。
大切なのは、一人で、そして二人だけで抱え込まないこと。
この記事をパートナーと共有することから、新しい家族の第一歩を踏み出してください。
あなたの勇気を、私たちは心から応援しています。

専門家に相談するなら「オンライン離婚相談 home」

男女関係や離婚の悩みって、
誰に相談したらいいんだろう…

弁護士やカウンセラーの事務所に
いきなり行くのはちょっと怖い…
\それなら…/
オンライン離婚相談 homeなら
来所不要、あなたのPC・スマホから
さまざまな専門家に相談できます。
夫婦関係や離婚に関する、あなたのお悩みに合った専門家とマッチング。いつでも好きなときにオンラインで相談できます。
夫婦関係の改善、離婚調停、モラハラ・DV、不倫・浮気、別居などさまざまなお悩みについて、専門家が寄り添います。匿名で利用できるため、プライバシーなどを気にせず、何でも安心してご相談いただけます。
24時間365日 オンライン相談できる

ビデオ通話、チャットからお好きな方法で相談いただけます。またプランも、1回ごとや月々定額(サブスク)からお選びいただけます。
厳選された専門家

弁護士、行政書士、探偵、離婚・夫婦問題カウンセラーなどの、経験豊富で厳選された専門家があなたの悩みに寄り添います。
離婚の公正証書が作成できる

離婚に強い女性行政書士に相談しながら、離婚条件を公正証書にすることができます。
公正証書にすることで、慰謝料や財産分与、養育費などが守られない場合、強制執行(給与、預貯金などの財産を差し押さえ)がカンタンになります。
養育費公正証書作成で数万円補助の可能性

養育費を取り決め、実際に受け取っているひとり親は、全体のわずか24.3%にとどまります。
この養育費未払い問題に、各自治体ではさまざまな支援制度が用意されています。
養育費に関する公正証書作成補助として、神奈川県は上限4万円、横浜市は上限3万円、川崎市は上限5万円などです(2025年4月時点)
参考:全国自治体の養育費支援、神奈川県の養育費支援

夫婦関係や離婚に関するお悩みを、24時間365⽇オンラインで解決できるオンライン離婚プラットフォーム。
夫婦関係の修復から、夫婦の話し合い、離婚相談、離婚後のサポートまで、専門家があなたの悩みに寄り添います。








