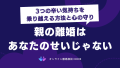「親や兄弟の面倒、どこまで見るのが義務なんだろう…」
「役所から『扶養照会』が届いたけど、どうすればいいの…?」
家族のことだからこそ、一人で抱え込み、漠然とした責任感や不安に押しつぶされそうになってはいませんか。
親族間の扶養問題は、「助けるのが当たり前」という感情論で語られがちです。
しかし、民法で定められた「扶養義務」には明確な範囲と程度があります。
この法的な線引きを知ることこそ、過度な自己犠牲を防ぎ、ご自身の生活を守るための盾となるのです。
曖昧な責任感に、これ以上悩む必要はありません。
まずは扶養義務の正しい知識を身につけ、ご自身の状況を客観的に見つめ直すことから始めましょう。
この記事では、親族の扶養問題に直面し、ご自身の法的な義務の範囲を知りたい方に向けて、主に以下を専門家視点でご説明します。
- 扶養義務の「範囲」と「義務のレベル」の明確な違い
- 税金や健康保険の「扶養」との関係性
- 役所からの「扶養照会」への具体的な対応方法
家族の問題は、時としてあなたの心を重く縛るかもしれません。
しかし、法律はあなたの生活を守るための味方にもなります。
この記事を最後まで読めば、その重荷の正体が分かり、心を軽くするための具体的な一歩を踏み出せるはずです。


扶養義務とは?税法上の「扶養」との違いを解説
「扶養義務」とは、生活できない親族を支える民法上の義務のことで、税金が安くなる「扶養控除」とは全くの別物です。
「役所から扶養照会が来た」「どこまで責任があるの?」と不安に思うかもしれませんが、この義務には法律上の明確な範囲と限界があります。
以下で、その内容と違いを具体的に解説します。
定められた親族を支える義務
民法が定める扶養義務とは、生活できない親族を援助する義務であり、重さが異なる2種類があります。
- 生活保持義務(強い義務):
自分と同じ生活水準を保障する義務。対象は夫婦と未成熟子のみです。 - 生活扶助義務(弱い義務):
自分の生活を犠牲にしない範囲で、余力があれば援助する義務。高齢の親や兄弟姉妹などが対象です。
そのため、高齢の親から援助を求められても、自分の生活で手一杯であれば法的に援助を強制されることはありません。
税金の「扶養控除」とは目的が異なる
税法上の「扶養控除」と民法上の「扶養義務」は、目的も意味も全く異なります。
- 税法上の扶養(扶養控除):
納税者の税負担を軽くするための制度であり、「権利」です。 - 民法上の扶養義務:
困窮する親族を経済的に支える法律上の「義務」です。
税金の扶養に親を入れたからといって、自分の生活を犠牲にするような重い扶養義務が自動的に発生するわけではありません。
この2つは全くの別物と理解してください。
生活保護制度より扶養義務が優先される
生活保護は、あらゆるものを活用してもなお困窮する場合の制度のため、申請があると親族(主に3親等内)に援助の可否を問う「扶養照会」が送られます。
この照会に法的な強制力はなく、「強制的に仕送りをさせられる」というのは誤解です。
特に兄弟や親への義務は「生活扶助義務」にあたるため、「自分の生活で手一杯なので援助は困難です」と回答すれば問題ありません。
扶養照会を過度に恐れる必要はないのです。







扶養義務を負う範囲と2つの義務レベル
「扶養義務」と一言でいっても、親族全員に対して同じ責任を負うわけではありません。
法律で定められた範囲があり、関係性によって義務の重さ(レベル)も異なります。
「疎遠な兄弟の面倒も見なければならないの?」
「親への援助はどこまでするべき?」
こうした疑問は、義務の範囲とレベルを正しく知ることで解消できます。
ここでは、誰が誰に対して義務を負うのか、そしてその義務の重さについて解説します。
扶養義務者の範囲はどこまでか
扶養義務を負うのは、民法で定められた一定の範囲の親族に限られます。
具体的には、以下の範囲の人が扶養義務者とされています。
また、特別な事情がある場合には、家庭裁判所の判断によって、叔父・叔母や甥・姪といった「三親等内の親族」が扶養義務を負うこともあります。
①生活保持義務:自分と同じ水準の生活を保障
これは、扶養義務の中で最も重いレベルの義務です。
「自分の生活レベルを下げてでも、相手に自分と同じ水準の生活をさせる義務」を意味します。
食事がやっとであれば、最後の一杯の粥を分かち合うようなイメージです。
この非常に強力な義務を負うのは、以下の2つの関係に限られます。
これら以外の関係では、生活保持義務を負うことはありません。
②生活扶助義務:余力のある範囲で援助
これは、生活保持義務に比べて軽いレベルの義務です。
「自分の社会的地位にふさわしい生活を維持した上で、なお経済的な余力があれば援助する義務」を指します。
自分の生活を切り詰めてまで援助する必要はありません。
生活保持義務の対象となる夫婦・親子以外の、ほとんどの扶養義務はこのレベルにあたります。
例えば、成人した子が親を扶養する場合や、兄弟姉妹間での扶養は、この生活扶助義務となります。
扶養義務の順位は当事者間の話し合いで決定
複数の扶養義務者がいる場合、誰がどの程度の扶養を行うべきか、その順位は法律で決まっていません。
例えば、高齢の親に対して子どもが複数いる場合、長男だから多く負担するといった決まりはないのです。
まずは、扶養義務者となる当事者間での話し合いによって決めるのが原則です。
もし話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立て、扶養の順位や分担額を決めてもらうことになります。







【関係性別】誰が誰に、どんな義務を負うのか
扶養義務の基本的な考え方を踏まえ、ここではより具体的に、関係性ごとにどのような義務が発生するのかを解説します。
ご自身の状況と照らし合わせて確認してみてください。
①夫婦間の扶養義務(婚姻費用)
夫婦は、互いに「生活保持義務」を負っています。
これは、お互いが同程度の生活水準を維持できるように、助け合う義務のことです。
この義務は、離婚が成立する前の別居期間中も継続します。
別居中、収入の少ない側が収入の多い側に対して請求する生活費のことを、法律上「婚姻費用」と呼びます。
これは、離婚の際に揉めることの多い重要な権利・義務の一つです。




②親から未成熟の子への扶養義務(養育費)
親は、経済的に自立していない未成熟の子に対して「生活保持義務」を負います。
これは親として当然の、非常に重い義務です。
親が離婚した場合でも、この義務がなくなることはありません。
離婚後に、子どもを監護・養育する親が、もう一方の親に対して請求する子どものための生活費が「養育費」です。
養育費は、子どもの健やかな成長のために不可欠な費用と言えます。



③成熟した子から親への扶養義務
経済的に自立した成人の子が、高齢の親などに対して負うのは「生活扶助義務」です。
これは「自分の生活に余力があれば援助する」という義務です。
したがって、自分の子どもの教育費や生活費で手一杯な状況で、無理をしてまで親に仕送りをする法的な義務はありません。
「親の面倒を見なければ」と過度な責任を感じる必要はないのです。
④兄弟姉妹間の扶養義務
兄弟姉妹の間で互いに負う義務も、親に対する義務と同じく「生活扶助義務」です。
これは、扶養義務の中でも比較的弱いレベルの関係と言えます。
兄弟姉妹から援助を求められたとしても、まずはご自身の生活を優先して構いません。
法的に扶養を強制されるケースは極めて稀であり、扶養義務者であるあなたに十分な経済的余力があり、相手が著しく困窮しているなどの特別な事情がなければ、援助を断っても問題はないでしょう。







扶養料の請求方法と扶養照会への対応
扶養義務は、具体的な金銭の請求、すなわち「扶養料」を求める権利・義務として現れることがあります。
また、親族が生活保護を申請した際には、役所から扶養が可能かどうかの「扶養照会」が届くこともあります。
こうした請求や照会には、法的な手続きや適切な対応方法が存在します。
ここでは、扶養料を請求する手順と、扶養照会への対応について解説します。
まずは当事者間の話し合い(協議)
扶養料の金額や支払い方法を決めるための最初のステップは、当事者同士での話し合い(協議)です。
扶養を必要とする側と、扶養義務を負う側とで、お互いの状況を誠実に伝え合うことが求められます。
話し合いで合意に至った場合は、後のトラブルを避けるため、合意内容を書面に残しておくことが重要です。
特に、金額や支払期間、支払い方法などを明確にした合意書を作成することをお勧めします。
話がまとまらなければ調停を申し立てる
当事者間の話し合いで解決しない場合や、相手が話し合いに全く応じない場合は、家庭裁判所に「扶養請求調停」を申し立てることができます。
調停は、裁判官と民間の有識者から選ばれた調停委員が間に入り、双方から事情を聞きながら、解決に向けた話し合いを進める手続きです。
判決を下す裁判とは異なり、あくまで当事者間の合意を目指す場となります。
調停で合意した内容は、裁判の判決と同じ法的効力を持つ「調停調書」として記録されます。
扶養料請求調停申立書の書き方と必要書類
扶養請求調停を申し立てるには、家庭裁判所に「申立書」と必要書類を提出します。
申立書の書式は、裁判所のウェブサイトからダウンロードするか、窓口で入手可能です。
申立書には、申立人(請求する側)と相手方(請求される側)の情報、請求の趣旨や理由などを記入します。
主な必要書類は以下の通りです。
相手方の収入資料も可能な限り準備しますが、不明な場合は調停手続きの中で照会を求めることもできます。
役所からの「扶養照会」が届いた場合の対応
親族が生活保護を申請すると、福祉事務所から扶養義務者に対して「扶養照会」の書面が届くことがあります。
これは、扶養(経済的援助)が可能かどうかを確認するためのアンケートであり、法的な強制力はありません。
書面が届いたら、無視せず、ご自身の経済状況を正直に回答することが大切です。
あなたの義務が、余力のある範囲での援助でよい「生活扶助義務」にあたる場合、現在の生活で手一杯であれば、「援助は困難です」と回答して問題ありません。
それによって罰則を受けたり、強制的に支払いを命じられたりすることはないのです。







扶養義務に関するよくある質問
扶養義務は、様々な制度や状況と関連して、多くの方が疑問を抱きやすいテーマです。
ここでは、特に質問の多い点について、Q&A形式で簡潔にお答えします。
Q. 健康保険の扶養とは関係ありますか?
A. 全く関係ありません。
健康保険の「扶養(被扶養者)」は、主に収入などの基準を満たした家族が、被保険者と同じ保険に加入できるという医療保険制度上の仕組みです。
民法上の「扶養義務」とは、根拠となる法律も目的も全く異なります。
健康保険の扶養に入っているからといって、民法上の扶養義務の重さが変わることはありません。
Q. 相続放棄をすれば義務もなくなりますか?
A. いいえ、なくなりません。
相続放棄は、亡くなった親の借金などのマイナスの財産を引き継がないための手続きです。
一方で、扶養義務は、生きている親族間の関係性に基づく義務です。
したがって、親の相続を放棄したとしても、兄弟姉妹など他の親族に対する扶養義務が消滅することはありません。
Q. 相手の収入が不明な場合はどうすれば?
A. 調停などの手続きの中で、照会を求めることができます。
当事者間の話し合いで相手が収入を明かさない場合でも、家庭裁判所の調停手続きを利用すれば、裁判所を通じて相手の勤務先などに収入を照会する「調査嘱託」などの方法があります。
弁護士に依頼すれば、弁護士会照会という制度を使って、より広範な調査が可能になる場合もあります。
Q. 海外など国内にいない家族でも義務は発生しますか?
A. 義務は発生しますが、実現は困難な場合があります。
扶養義務は、当事者がどこに住んでいても、日本の法律が適用される限り発生します。
しかし、海外に住む相手に対して、日本の裁判所が決めた扶養料の支払いを強制することは、国際的な条約や相手国の法律が絡むため、非常に複雑で困難を伴うのが実情です。
このようなケースでは、国際家事事件に詳しい弁護士への相談が不可欠となります。
まとめ:扶養義務の知識で、自分と家族を守る
この記事で、「扶養義務の範囲と2つの義務レベル」「関係性別の具体的な義務内容」「扶養照会への対応方法」などについて説明してきました。
家族の問題だからこそ、「助けるのが当たり前」という感情論や道徳観によって、追い詰められてはいませんか。
しかし、民法が定める扶養義務には、明確な範囲と限度が定められています。
この法的な線引きを知ることこそ、過度な自己犠牲を防ぎ、ご自身の生活を守るための盾となるのです。
まずはこの記事を参考に、ご自身が負う義務の範囲と程度を正しく理解し、客観的に状況を整理してみてください。
兄弟間での親の介護費用の分担や、役所から届いた扶養照会への対応など、当事者だけでの解決が難しい問題もあります。
そのような場合は、一人で抱え込まず、専門家へ相談することで、より迅速かつ円満に解決できる可能性が高まります。
法律は、あなたを縛るためだけにあるのではありません。
ご自身の生活を守りながら、家族と向き合うための、客観的な道しるべにもなってくれるでしょう。
この記事で得た知識を元に、ご自身の状況を整理することが、複雑な問題を解きほぐし、心の負担を軽くするための、確かな第一歩です。
専門家に相談するなら「オンライン離婚相談 home」

男女関係や離婚の悩みって、
誰に相談したらいいんだろう…

弁護士やカウンセラーの事務所に
いきなり行くのはちょっと怖い…
\それなら…/
オンライン離婚相談 homeなら
来所不要、あなたのPC・スマホから
さまざまな専門家に相談できます。
夫婦関係や離婚に関する、あなたのお悩みに合った専門家とマッチング。いつでも好きなときにオンラインで相談できます。
夫婦関係の改善、離婚調停、モラハラ・DV、不倫・浮気、別居などさまざまなお悩みについて、専門家が寄り添います。匿名で利用できるため、プライバシーなどを気にせず、何でも安心してご相談いただけます。
24時間365日 オンライン相談できる

ビデオ通話、チャットからお好きな方法で相談いただけます。またプランも、1回ごとや月々定額(サブスク)からお選びいただけます。
厳選された専門家

弁護士、行政書士、探偵、離婚・夫婦問題カウンセラーなどの、経験豊富で厳選された専門家があなたの悩みに寄り添います。
離婚の公正証書が作成できる

離婚に強い女性行政書士に相談しながら、離婚条件を公正証書にすることができます。
公正証書にすることで、慰謝料や財産分与、養育費などが守られない場合、強制執行(給与、預貯金などの財産を差し押さえ)がカンタンになります。
養育費の公正証書作成で数万円補助の可能性

養育費を取り決め、実際に受け取っているひとり親は、全体のわずか24.3%にとどまります。
この養育費未払い問題に、各自治体ではさまざまな支援制度が用意されています。
養育費に関する公正証書作成補助として、神奈川県は上限4万円、横浜市は上限3万円、川崎市は上限5万円などです(2025年4月時点)
参考:全国自治体の養育費支援、神奈川県の養育費支援


夫婦関係や離婚に関するお悩みを、24時間365⽇オンラインで解決できるオンライン離婚プラットフォーム。
夫婦関係の修復から、夫婦の話し合い、離婚相談、離婚後のサポートまで、専門家があなたの悩みに寄り添います。