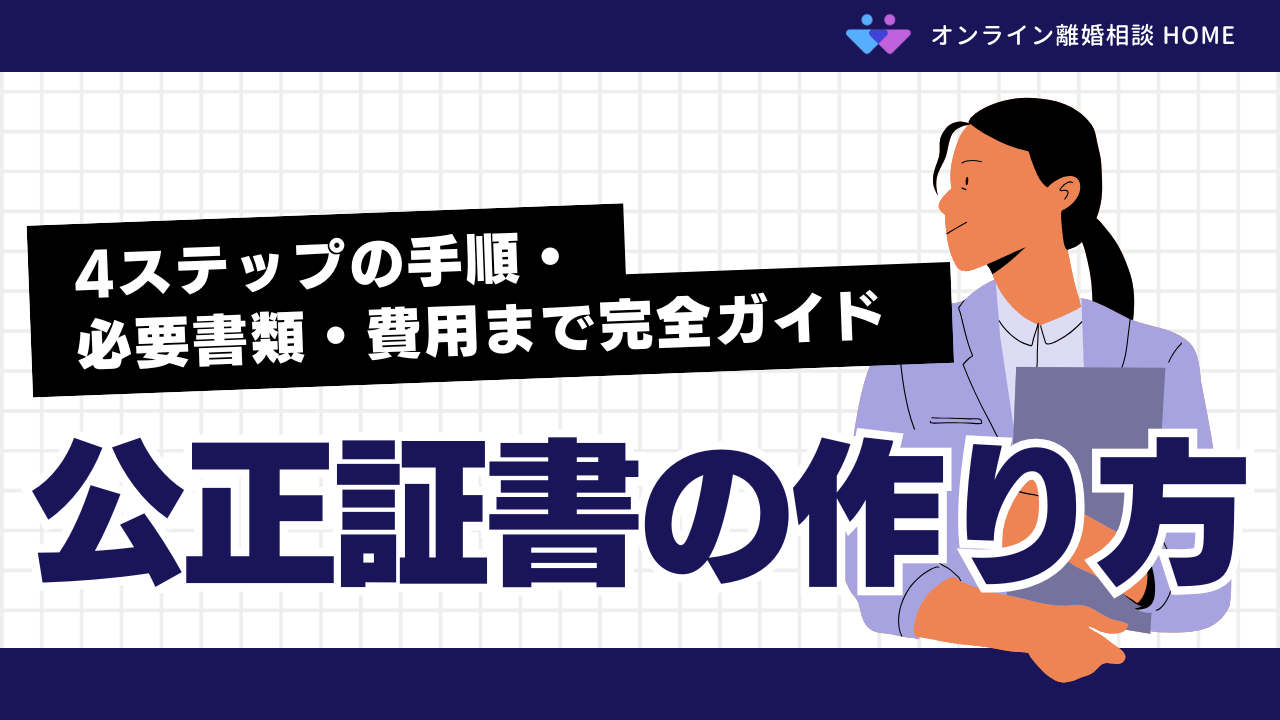「公正証書って聞いたけど、作り方が難しそう…」
「費用はどれくらい?そもそも自分で手続きできるのかな…」
大切な約束事を形に残したいと考えたとき、このような疑問や不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。
公正証書は、離婚時の取り決めや遺言、重要な契約などを法的に確かなものにし、将来のトラブルを防ぐための非常に有効な手段です。
その作り方は、ポイントを押さえれば決して難しくありません。
この記事では、公正証書の基本的な知識から、具体的な作成手順(4ステップ)、必要な準備、費用、さらには専門家サポートの活用法まで、あなたが知りたい情報を分かりやすく解説しています。
この記事を読み進めれば、公正証書作成への不安が解消され、スムーズに手続きを進めるための道筋が見えてくるはずです。
この記事では、大切な約束事を確かな形に残したいと考えている方に向けて、主に以下を専門家の視点でご説明します。
- 公正証書の基本的な効力とメリット、活用場面
- 公正証書作成の具体的な4ステップと必要な準備(書類・費用)
- 弁護士や行政書士など専門家サポートの利用判断基準
公正証書の作成は、あなたの未来への大切な備えとなります。
この記事が、その準備を安心して進めるための一助となれば幸いです。
ぜひ最後までお読みいただき、参考にしてください。


公正証書とは?基本とメリット・活用場面
公正証書は、将来のトラブルを未然に防ぐための強力な手段です。
離婚や金銭トラブル、相続などの重要な取り決めを、第三者である公証人が法的に裏付けてくれることで、安心して合意内容を守ることができます。
「相手が約束を守らなかったらどうしよう…」という不安がある方にとって、公正証書は心強い後ろ盾となります。
言った・言わないの争いを避け、約束を形に残すことができるため、信頼関係が壊れた後でも冷静に対処できます。
以下で詳しく解説していきます。
公正証書が持つ法的な効力とは
公正証書は「執行力のある証書」として、裁判所の判決を経ずに強制執行が可能です。
つまり、たとえば慰謝料や養育費の支払いが滞ったとき、公正証書に記載されていれば裁判をしなくても差し押さえができるのです。
この効力は「強制執行認諾文言」という特別な文言を記載することで得られます。
そのため、公正証書を作成する際は、この文言が入っているかどうかを必ず確認することが大切です。
口約束ではどうにもならない金銭の支払いなども、公正証書があるだけで大きな抑止力になります。


公正証書を作成するメリット3つ
公正証書には以下のような主なメリットがあります。
- 強制執行が可能
相手が約束を破った場合でも、裁判をせずに財産を差し押さえることができる。 - 第三者による証明力がある
公証人という中立な第三者が内容を確認・記録することで、後々の争いを防げる。 - 証拠としての信頼性が高い
裁判でも証拠として高く評価されるため、万が一の時の法的リスクにも対応できる。
これらの利点により、公正証書は「口約束よりもずっと安心できる証拠」として広く活用されています。


どんな場合に利用?遺言・離婚・契約
公正証書はさまざまな場面で活用されています。
中でも多いのは以下のケースです。
- 遺言:法的効力のある「公正証書遺言」は、争いを避けるために最も確実な形式とされています。
- 離婚:養育費や慰謝料など、将来の支払いが関係する場合には特に有効です。
- 契約:金銭貸借・不動産の賃貸借契約・示談書など、ビジネスや個人間での合意にも使用されています。
これらの例に共通するのは「合意内容をきちんと形にして残したい」というニーズです。
作成前に知っておきたい注意点
公正証書を作成する際は、いくつかの注意点もあります。
これらの点を押さえておけば、「せっかく作ったのに使えない…」という事態を防ぐことができます。







公正証書作成の準備:必要書類・費用
公正証書をスムーズに作成するためには、事前の準備が欠かせません。
「いざ公証役場に行っても書類が足りなかった…」といったことにならないよう、必要な情報を整理しておくことが安心につながります。
また、費用についてもあらかじめ目安を知っておくことで、余計なトラブルや不安を防ぐことができます。
以下では、公正証書の作成に必要な書類や費用、予約の流れなどについて詳しく解説していきます。
作成に必要な書類チェックリスト
公正証書の内容によって必要書類は異なりますが、以下は一般的な離婚に関する公正証書で求められる主な書類です。
- 本人確認書類:運転免許証やマイナンバーカードなど。
- 住民票や戸籍謄本:離婚協議書に記載される氏名・住所を確認するために必要です。
- 財産関係資料:不動産の登記簿謄本、預金通帳のコピーなど。
- 取り決め内容の書面:養育費や慰謝料など、合意内容が書かれた離婚協議書(案)。
あらかじめコピーを取り、原本と一緒に持参しておくとスムーズです。
事前に決めておくべき契約内容
公正証書を作成するには、当事者間で内容をしっかり合意しておく必要があります。
特に次のような項目は事前に決めておくことが重要です。
これらの内容が曖昧なままだと、公証人から修正を求められたり、作成ができない場合もあります。
公証役場の探し方と予約方法
公正証書の作成は、全国の公証役場で行えます。
探し方と予約のポイントは以下の通りです。
- 法務省のサイトで検索:最寄りの公証役場を地名や都道府県別に探せます。
- 電話またはメールで予約:多くの公証役場では、事前に予約が必要です。
- 内容の事前相談も可能:簡単な内容確認や必要書類の案内を、作成前に行ってくれます。
予約時には、「離婚に関する公正証書を作りたい」など、目的を明確に伝えると話が早く進みます。


公証人手数料の目安と計算例
公正証書作成には、公証人に支払う手数料が発生します。
以下が目安です。
- 定額の手数料
例えば慰謝料の支払いを定める公正証書は、金額に応じて手数料が決まります。
例)慰謝料300万円の場合:約1万7,000円〜2万円前後。 - 証書が2通以上必要な場合は写し代も発生。
また、公証人が出張する場合は、出張料や交通費も加算されます。
事前に見積もりを依頼しておくと安心です。



公正証書の作り方:具体的な4ステップ
公正証書の作成と聞くと、「なんだか難しそう…」「手続きが複雑なのでは?」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、基本的な流れを理解し、順を追って進めれば、決して特別なことではありません。
大切な約束事を法的に確かな形にするための、重要なプロセスなのです。
公正証書の作成は、主に公証役場という場所で、公証人という法律の専門家が関与して行われます。
事前に流れを把握しておくことで、不安なくスムーズに手続きを進めることができるでしょう。
以下で、公正証書が完成するまでの具体的な流れを、大きく4つのステップに分けて解説していきます。
STEP1:公証役場へ連絡・相談
まず、公正証書を作成したいと考えたら、お近くの公証役場へ連絡することから始めます。
全国の公証役場は、日本公証人連合会のウェブサイトで検索可能です。
電話などで連絡し、どのような内容の公正証書を作成したいのか(例:離婚の養育費について、遺言についてなど)を伝え、相談の日時を予約しましょう。
この最初の相談で、今後の流れや必要となる書類について説明を受けることができます。
公証役場によっては予約が必須の場合や、特定の種類の公正証書(例:遺言)は担当する公証人が決まっている場合もあるため、事前の連絡は重要です。



STEP2:必要書類の提出と内容確認
公証人との打ち合わせや、公正証書作成当日までに、指示された必要書類を準備し、提出する必要があります。
一般的には、当事者それぞれの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)、印鑑登録証明書と実印、そして公正証書に記載したい契約内容に関する資料(離婚協議のメモ、遺産のリスト、契約書の案など)が求められます。
どのような書類が必要かは、作成する公正証書の種類や内容によって異なりますので、必ず公証人に確認してください。この段階で、公正証書に盛り込みたい内容を公証人に正確に伝え、法的な問題がないかなどを確認してもらうことになります。
STEP3:公証人による証書案作成
提出された書類と、当事者からの聴取内容に基づいて、公証人が公正証書の原案を作成します。
公証人は法律の専門家として、当事者の意向を尊重しつつ、法的に有効で明確な内容の文書を作成する役割を担っています。
通常、原案が完成すると、事前にその内容を確認する機会が設けられます。
この段階で、記載内容に誤りがないか、自分たちの意図が正確に反映されているかを十分に確認し、もし修正が必要な点があれば公証人に伝えましょう。
納得いくまで内容を詰めることが大切です。
STEP4:役場での署名・捺印で完成
公正証書の原案の内容に問題がなければ、最終的な作成日時の予約を取ります。
当日は、原則として契約に関わる当事者全員(遺言の場合は遺言者と証人2名)が公証役場に出向き、公証人の面前で手続きを行います。
公証人が完成した公正証書の内容を読み上げ、当事者がその内容を確認した上で、署名と捺印(通常は実印)をします。
最後に公証人も署名捺印し、公正証書は完成となります。
作成にかかった費用(公証人手数料)は、通常この時に現金で支払います。
完成した公正証書の原本は公証役場で保管され、当事者には正本または謄本が交付されます。





専門家サポート:弁護士・行政書士の活用
公正証書の作成は、ご自身で公証役場とやり取りして進めることも可能です。
しかし、「手続きが複雑でよく分からない…」「自分で書類を作るのは不安だ」「相手と直接やり取りしたくない」と感じる方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合には、弁護士や行政書士といった専門家のサポートを活用することも有効な選択肢となります。
専門家に依頼すれば費用はかかりますが、手続きの負担軽減や、より確実で有利な内容の公正証書を作成できる可能性が高まります。
ただし、どの専門家に依頼すべきかは、ご自身の状況によって異なります。
「費用をかけてでも、しっかりサポートしてほしい」「書類作成だけ手伝ってほしい」など、求めるサポートの内容によって適切な専門家は変わってくるでしょう。
以下で、専門家サポートの利用について、判断基準や各専門家の役割、費用などを解説します。
自分で作成?専門家に依頼?判断基準
公正証書を自分で作成するか、専門家に依頼するかは、いくつかの点を考慮して判断しましょう。
まず、作成したい公正証書の内容が比較的単純で、当事者間の合意が完全にできている場合は、ご自身で作成することも十分可能です。
例えば、定型的な金銭消費貸借契約(個人間の少額な貸し借り)などは、本人作成のハードルはそれほど高くないかもしれません。
一方で、以下のような場合は、専門家への依頼を検討するメリットが大きいでしょう。
- 遺産分割が複雑な遺言を作成したい場合
- 離婚に伴う財産分与に不動産が含まれるなど、権利関係が複雑な場合
- 相手方との間に対立があり、交渉が必要となりそうな場合
- ご自身で手続きを進める時間がない、あるいは手続きに不安がある場合
専門家は、あなたの状況に応じた最適なアドバイスとサポートを提供してくれます。
弁護士に相談するメリットと費用
弁護士は、法律に関するあらゆる問題に対応できる専門家です。
公正証書作成においては、単なる書類作成のサポートだけでなく、内容に関する法的なアドバイス、相手方との交渉代理、そして万が一紛争になった場合の調停や訴訟対応まで、一貫して依頼することができます。
特に、離婚や相続などで相手方との間に対立がある場合や、法的に複雑な問題を抱えている場合には、弁護士に相談・依頼することが非常に有効です。
ただし、弁護士費用は他の専門家と比較して高額になる傾向があります。
相談料(30分5,000円~1万円程度が相場)、公正証書作成のサポートに関する着手金や報酬金などが必要となり、総額で数十万円以上かかるケースも少なくありません。
費用対効果をよく考え、まずは法律相談を利用してみるのが良いでしょう。



行政書士ができること・費用相場
行政書士は、「権利義務又は事実証明に関する書類」作成の専門家です。
公正証書作成に関しては、主に依頼者の意向に基づいた公正証書の原案作成や、公証役場との連絡調整、必要書類の収集代行などをサポートします。
夫婦間の合意が概ねできている場合の離婚協議書の原案作成や、遺言書の原案作成サポートなどで利用されることが多いです。
弁護士とは異なり、相手方との交渉代理や具体的な法律紛争に関する相談(非弁行為にあたるため)はできません。
そのため、当事者間の合意形成が前提となる場合に適しています。
費用は弁護士に比べて抑えられる傾向にあり、公正証書の原案作成サポートであれば、数万円から十数万円程度が相場となることが多いようです(内容により変動します)。
代理人による作成は可能か?
公正証書の作成は、原則として当事者本人が公証役場に出向いて行う必要があります。
これは、公証人が当事者の本人確認と意思確認を直接行うためです。
しかし、やむを得ない事情(遠方に住んでいる、病気で外出困難など)がある場合には、委任状を作成し、代理人を立てて手続きを進めることが認められています。
代理人は、親族や友人でも構いませんが、手続きの正確性を期すためには弁護士や行政書士に依頼するのが一般的です。
代理人が手続きを行う場合、委任状の他に、本人の印鑑登録証明書や代理人の身分証明書など、追加の書類が必要となります。
ただし、遺言公正証書については、遺言者の意思を直接確認する必要性が特に高いため、原則として代理人による作成は認められていません(公証人が遺言者の元へ出張することは可能です)。
代理人申請が可能かどうかは、事前に公証役場に確認しましょう。



「公正証書の作り方」に関するよくある質問
公正証書の作成を具体的に考え始めると、細かな疑問点が色々と出てくることでしょう。
費用は誰が払うの?期間はどれくらい?など、気になる点は多いはずです。
多くの方が疑問に思われる点について、事前に知っておくことで、よりスムーズに手続きを進めることができます。
ここでは、公正証書の作り方に関して寄せられることの多い代表的な質問について、Q&A形式で分かりやすくお答えしていきます。
Q. 作成期間はどれくらいかかりますか?
公正証書の作成にかかる期間は、作成する内容の複雑さや、公証役場の混雑状況、必要書類の準備状況によって異なります。
一般的には、最初の相談から公正証書の完成まで、数週間から1ヶ月程度を見込んでおくと良いでしょう。
遺言のように内容が定型的でない場合や、当事者間の調整に時間がかかる場合、修正が多い場合などは、さらに時間がかかることもあります。
余裕をもったスケジュールで準備を進めることをお勧めします。
Q. 公証役場に行かなくても作れますか?
公正証書の作成は、公証人が当事者の本人確認と意思確認を直接行う必要があるため、原則として当事者本人が公証役場に出向く必要があります。
ただし、やむを得ない事情がある場合には、例外的な方法も認められています。
委任状を作成し、代理人を立てて手続きを行う方法(ただし遺言公正証書は原則不可)や、病気などで外出が困難な場合に公証人に自宅や病院などへ出張してもらう方法があります。
出張には別途、日当や交通費がかかりますので、事前に公証役場へご相談ください。
Q. 費用は誰が負担するのが一般的?
公正証書の作成費用(公証人手数料)を誰が負担するかについて、法律上の明確な決まりはありません。
そのため、当事者間の話し合いによって決めるのが一般的です。
契約の種類によって、ある程度の慣習が見られる場合はあります。
例えば、離婚給付契約では夫婦で折半するか収入の多い側が負担する、遺言では遺言者本人が負担する、金銭消費貸借契約では借主が負担するといったケースが多いようですが、これもあくまで傾向です。
後々のトラブルを避けるためにも、作成前に費用負担についてもしっかりと話し合っておくことが望ましいでしょう。
Q. 遺言公正証書の証人は誰でもいい?
遺言公正証書を作成する際には、信頼できる証人2名の立会いが必要です。
しかし、誰でも証人になれるわけではありません。
法律により、未成年者、推定相続人(相続人になる予定の人)、受遺者(遺言で財産を受け取る人)、およびこれらの人々の配偶者や直系血族は、利害関係があるため証人になることができません(民法第974条)。
友人や知人など、利害関係のない成人の方に依頼するのが一般的です。
もし適当な証人が見つからない場合は、公証役場で紹介してもらえることもありますので(別途費用がかかる場合があります)、相談してみましょう。
Q. 電子公正証書について教えて
近年、様々な手続きの電子化が進んでいますが、公正証書については、まだ一部の手続きに限られています。
例えば、株式会社などの定款認証については電子認証制度が導入されています。
しかし、遺言公正証書や離婚給付等契約公正証書、金銭消費貸借契約公正証書など、個人の権利義務に関する多くの公正証書は、依然として紙の文書で作成され、公証役場で原本が保管されるのが原則です(2025年5月現在)。
将来的に電子化が進む可能性はありますが、現状では書面での作成が主流であるとご理解ください。
最新の動向については、日本公証人連合会のウェブサイトや公証役場にご確認ください。
まとめ:公正証書で未来への安心を
この記事では、公正証書の基本、メリット、作り方(4ステップ)、費用、専門家活用を解説しました。
公正証書は将来のトラブルを防ぐ有効な手段です。
手続きは複雑に感じても、知識があれば大丈夫でしょう。
この記事を参考に、まず目的を明確にし、準備を始めてください。
それが確かな一歩となります。
離婚や遺言など複雑な場合は専門家相談も有効でした。
私たち「home」提携の専門家もサポート可能です。
気軽に検討してみてはいかがでしょうか。
確かな形を作ることで、不安は安心へと変わります。
前向きな未来に繋がるはずです。
この記事を元に、大切な約束事を形にする一歩を。
あなたの未来への備えを応援しています。

専門家に相談するなら「オンライン離婚相談 home」

男女関係や離婚の悩みって、
誰に相談したらいいんだろう…

弁護士やカウンセラーの事務所に
いきなり行くのはちょっと怖い…
\それなら…/
オンライン離婚相談 homeなら
来所不要、あなたのPC・スマホから
さまざまな専門家に相談できます。
夫婦関係や離婚に関する、あなたのお悩みに合った専門家とマッチング。いつでも好きなときにオンラインで相談できます。
夫婦関係の改善、離婚調停、モラハラ・DV、不倫・浮気、別居などさまざまなお悩みについて、専門家が寄り添います。匿名で利用できるため、プライバシーなどを気にせず、何でも安心してご相談いただけます。
24時間365日 オンライン相談できる

ビデオ通話、チャットからお好きな方法で相談いただけます。またプランも、1回ごとや月々定額(サブスク)からお選びいただけます。
厳選された専門家

弁護士、行政書士、探偵、離婚・夫婦問題カウンセラーなどの、経験豊富で厳選された専門家があなたの悩みに寄り添います。
離婚の公正証書が作成できる

離婚に強い女性行政書士に相談しながら、離婚条件を公正証書にすることができます。
公正証書にすることで、慰謝料や財産分与、養育費などが守られない場合、強制執行(給与、預貯金などの財産を差し押さえ)がカンタンになります。
養育費公正証書作成で数万円補助の可能性

養育費を取り決め、実際に受け取っているひとり親は、全体のわずか24.3%にとどまります。
この養育費未払い問題に、各自治体ではさまざまな支援制度が用意されています。
養育費に関する公正証書作成補助として、神奈川県は上限4万円、横浜市は上限3万円、川崎市は上限5万円などです(2025年4月時点)
参考:全国自治体の養育費支援、神奈川県の養育費支援

夫婦関係や離婚に関するお悩みを、24時間365⽇オンラインで解決できるオンライン離婚プラットフォーム。
夫婦関係の修復から、夫婦の話し合い、離婚相談、離婚後のサポートまで、専門家があなたの悩みに寄り添います。