「どこに相談すれば安心なのか分からない…」
「無料で話せる場所があるのかな…」
初めて離婚相談を考えた時、こんな不安を抱えている方もいるでしょう。
しかし、公的機関から専門家まで5種類の窓口を知れば、自分に最適な相談先が見つかります。
この記事では、それぞれの窓口が対応する悩みや利用方法を詳しくご説明します。
まずは安心の一歩を踏み出しましょう。
この記事では、離婚の相談先に困っている方に向けて、主に以下を専門家視点でご説明します。
- 離婚相談窓口5種類の特徴と選び方
- 無料・有料それぞれの利用条件と流れ
- 相談前に準備すべきポイント
誰にも話せずに抱え込む前に、まずはこの記事を参考にしてみてください。専門家や公的機関の力を借りて、不安を具体的な解決策へとつなげましょう。


離婚の相談窓口は5種類!悩み別の選び方【完全版】
離婚を考え始めたとき、その大きな問題に一人で立ち向かうのは、あまりにも重く、辛いものです。
幸い、今の日本には、あなたの状況や悩みに応じて、様々な専門知識を持つ相談窓口が存在します。
「私のこの悩み、一体誰に何を相談すればいいの…」と途方に暮れてしまう前に、まずはどのような選択肢があるのかを知ることが、解決への最も重要な第一歩となります。
間違った窓口を選んでしまうと、時間や費用が無駄になるだけでなく、かえって話がこじれてしまう可能性もあるのです。
以下では、離婚の相談ができる代表的な5種類の窓口と、それぞれの特徴、そしてあなたの悩みに合わせた最適な選び方について、分かりやすく解説していきます。
①オンライン離婚の窓口 home
「弁護士事務所は敷居が高い…」「誰に相談すればいいか分からない」そう感じていませんか?
オンライン離婚の窓口 home では、夫婦関係や離婚に関するお悩みを、24時間365⽇オンラインで解決できます。離婚問題に強い弁護士や、行政書士、カウンセラー、探偵などの専門家に、チャットやビデオ通話でオンラインで相談できます。
夫婦関係の修復から、慰謝料・養育費の取り決めを確実にするための公正証書作成サポートまで、あなたの状況に合った専門家が寄り添います。
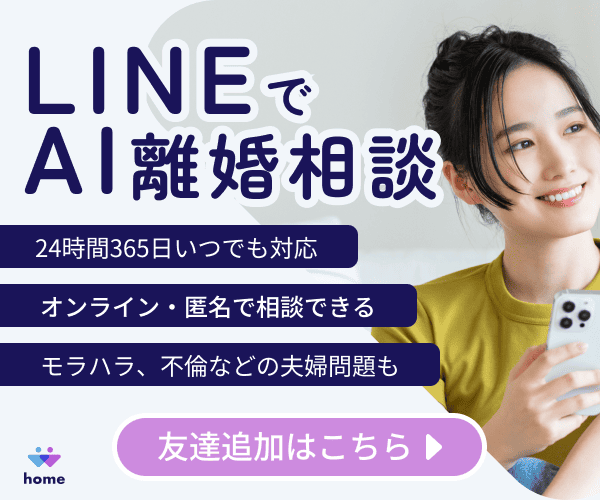
②市区町村役場などの公的な相談窓口
まず検討したいのが、お住まいの市区町村役場が設けている相談窓口です。
多くの自治体では、弁護士による無料法律相談や、女性相談、母子・父子自立支援員による相談などが定期的に実施されています。
「何から始めればいいか分からない」「まずは気軽に話を聞いてほしい」という方に、最適な最初のステップと言えるでしょう。
③法テラス(日本司法支援センター)
法テラスは、国によって設立された、法的なトラブル解決のための「総合案内所」です。
経済的に余裕のない方でも、法律の専門家によるサポートを受けられるようにするための制度が整っています。
収入や資産が一定の基準以下であるなどの条件を満たせば、同じ案件について原則3回まで、無料の法律相談を受けることが可能です。
さらに、弁護士に依頼する際の着手金や実費などを立て替えてもらい、後で分割返済していく「民事法律扶助制度」もあります。
費用面で弁護士への依頼をためらっている方にとって、非常に心強い味方です。
④弁護士・行政書士などの法律事務所
慰謝料や財産分与で相手と話がまとまらない、あるいは調停や裁判といった法的手続きを考えている場合には、弁護士などの法律専門家への相談が不可欠となります。



⑤夫婦問題カウンセラーなどの民間相談機関
「離婚すべきかどうか、まだ迷っている」「相手との関係を修復したい」といった、ご自身の心の悩みや夫婦関係そのものに関する相談は、夫婦問題カウンセラーが専門です。
法律的な解決ではなく、お二人のコミュニケーションの改善や、感情の整理を手伝い、夫婦が今後どのような選択をすべきか、その道筋を一緒に探してくれます。
法的な手続きに入る前に、まずはご自身の気持ちを専門家と整理したい、という場合に適した相談先と言えるでしょう。



【無料】公的な離婚相談窓口とサポート内容
公的な窓口は費用をかけずに相談できる頼れる存在です。
「お金がないけれど、まずは相談したい…」「誰に話せばいいか分からない…」と感じる方も多いでしょう。
自治体や国の支援を活用することで、初期段階の情報収集や手続きの案内を受けられます。
以下で詳しく解説していきます。
市区町村役場でできること・できないこと
市区町村役場の「家庭相談窓口」では、離婚手続きや子育て、生活支援に関する情報提供が受けられます。
専任の相談員が話を聞き、適切な制度や手続き先を紹介してくれるのが大きな強みです。
ただし、市区町村では法的アドバイスや調停代理はできません。
あくまで情報提供と手続き案内が中心となるため、具体的な契約書作成や裁判代理が必要な場合は他機関を検討してください。
法テラスの利用条件と相談の流れ
法テラス(日本司法支援センター)は、収入・資産が一定基準以下の方に無料法律相談や弁護士費用立替制度を提供しています。
収入の目安は「単身月収約21万円以下、資産約100万円以下」などの基準を満たす必要があります。
相談の流れは①電話またはオンラインで予約 ②必要書類を提出 ③初回無料相談(最大3回) ④立替制度申請 となります。
書類の準備や申請手続きは法テラス職員がサポートしてくれるため、法的手続き初心者でも安心して利用可能です。
女性センター等の専門相談窓口の対象と特徴
女性センターや男女共同参画センターなどは、特に女性の視点に立った相談支援を行います。
DVやモラハラ、子育てと離婚の両立など、性別特有の悩みに配慮した専門相談員が在籍しています。
秘密厳守でカウンセリングを受けられ、市区町村窓口よりも深い心理的ケアや事例共有が可能です。
利用対象は主に女性ですが、両親や家族の相談にも対応している場合がありますので、詳細は各センターに確認してください。



【専門家】弁護士・カウンセラー等の相談窓口
専門家への相談は、具体的な解決策や手続きを確実に進めるうえで有効です。
「法的な争いを整理したい」「心の傷を癒したい」「証拠収集を任せたい」という方には、各分野のプロが力になります。
専門家ごとの得意分野を理解し、最適な窓口を選ぶことが重要です。
以下で詳しく解説していきます。
法律問題や慰謝料請求なら弁護士法人へ相談
弁護士は離婚調停・訴訟の代理や慰謝料請求の交渉、財産分与の法的アドバイスが可能です。
法律上の主張や証拠の整理、期日対応まで一括して任せられるため、安心して争点を訴えることができます。
具体例として、不貞行為の慰謝料請求では、写真や録音などの証拠を法律的に評価し、適切な金額を算定して代理交渉を行います。
費用は弁護士事務所によって違いますが、着手金と報酬金の明確化された料金体系を事前に確認しましょう。


書類作成なら行政書士という選択肢
行政書士は離婚協議書や公正証書の作成に特化した専門家です。
協議段階で合意内容を正しく反映させ、法的拘束力のある公正証書にまとめることで、後日のトラブルを防止できます。
行政書士に依頼するメリットは、弁護士より比較的低コストで文書作成の支援が受けられる点です。
ただし調停や訴訟代理はできないため、法的代理が必要な場合は弁護士との併用を検討してください。







心の悩みや夫婦関係の修復ならカウンセラー
夫婦問題カウンセラーや臨床心理士は、離婚を決断する前後の心理的ケアを担当します。
感情の整理やコミュニケーション改善のための対話技法を用い、冷静な判断をサポートします。
たとえば「話し合いが感情的になる」「子どもへの影響が心配」という悩みに対し、対等な対話方法やストレス緩和のアドバイスを提供します。
料金は機関によりますが、オンライン相談を含む多様な形式が利用できる点が特徴です。


浮気調査なら探偵事務所への依頼も
配偶者の行動確認や証拠収集を専門とする探偵事務所では、浮気調査や素行調査が依頼できます。
プロの調査員が張り込みや尾行を行い、写真や映像による証拠を取得。
これらの証拠は慰謝料請求や親権争いの際に強力な裏付けとなります。
ただし費用は高額になりやすいため、見積もりや成功報酬型の契約内容をしっかり確認してください。




離婚相談を有意義にするための準備と当日の対応
「聞きたいことがたくさんあったのに、緊張して頭が真っ白になってしまった…」
「何から話せばいいか分からず、ただ愚痴を言って終わってしまった…」
こうしたことは、実はよくあるケースなのです。
せっかくの一歩を無駄にしないためにも、相談を有意義にするためのポイントをしっかり押さえておきましょう。
離婚について誰かに相談すると決めても、限られた時間の中で、ご自身の状況を正確に伝え、的確なアドバイスをもらうためには、事前の「準備」と当日の「対応」が非常に重要になります。
ここでは、離婚相談の前にまとめておくべきこと、相談当日に聞くべき質問や効果的な伝え方のコツ、そして相談後の次のステップについて、具体的に解説していきます。
相談前にまとめておくべきことリスト【一覧】
相談時間を最大限に活用するため、事前にご自身の状況や質問したいことを簡単なメモにまとめておくことを強くお勧めします。
これがあるだけで、話の要点が整理され、相談相手もあなたの状況を素早く正確に理解できます。
- これまでの経緯
いつから関係が悪化したのか、離婚の主な原因は何か、といった状況を時系列で簡単に整理します。 - 相談したいことの要点:
「離婚できるか知りたい」「親権を取りたい」「慰謝料の相場が知りたい」など、最も聞きたいことを箇条書きにします。 - 希望する結果
離婚したいのか、それとも関係修復を望むのか、ご自身の最終的な目標を伝えます。 - 関連資料の準備
収入が分かる資料(源泉徴収票など)や、不貞行為の証拠など、相談内容に関連する資料があれば持参しましょう。



当日聞くべき質問と効果的な伝え方のコツ
相談当日は、感情的にただ不満をぶつけるのではなく、事実を基に、冷静に、そして具体的に話すことを心がけましょう。
事前にまとめたメモを見ながら話すと、伝え漏れを防げます。
また、受け身になるのではなく、積極的に質問することも大切です。
「私の状況での法的な選択肢は何ですか?」「考えられるリスクは何でしょう?」「もし依頼した場合の費用は、どのくらいになりますか?」など、具体的な質問をすることで、より実践的なアドバイスを引き出すことができます。



相談後の次のステップへの進め方
相談を終えたら、それだけで満足せず、必ず次の具体的なアクションに繋げることが重要です。
専門家からのアドバイスを基に、ご自身の状況が客観的に見えてきたはず。
まずは、もらったアドバイスを忘れないうちにメモにまとめ、内容を整理しましょう。
その上で、「相手と一度、冷静に話し合ってみる」「財産分与のための資料を集める」「弁護士に正式に依頼する」など、次に取るべき具体的な一歩を決め、実際に行動に移すことが、問題解決への着実な歩みとなります。



離婚問題に強い弁護士・法律事務所の探し方
離婚問題に、慰謝料や財産分与といった法的な交渉が必要な場合、法律の専門家である弁護士への相談が、最善の解決への近道となります。
しかし、弁護士と一口に言っても、その専門分野は様々です。
「弁護士なら、誰に頼んでも同じだろう…」これは大きな誤解です。
例えば、お腹が痛いときに眼科に行かないのと同じように、離婚問題は、離婚や男女問題に精通した経験豊富な弁護士に依頼することが、結果を大きく左右します。
以下では、あなたの味方となってくれる、離婚問題に強い弁護士や法律事務所の具体的な探し方と、費用を抑えるためのポイントについて解説します。
ネットでの探し方と比較検討のポイント
現在では、インターネットを使って、離婚問題に強い弁護士や法律事務所を効率的に探すことができます。
法律事務所のウェブサイトを見る際には、以下のポイントをチェックしましょう。
- 離婚問題の解決実績
これまでにどれくらいの離婚案件を扱ってきたか、具体的な解決事例が掲載されているか。 - 専門性の表示
「離婚・男女問題専門チーム」など、専門性を明確に打ち出しているか。 - 料金体系の明確さ
費用について、分かりやすく明記されているか。
一つの事務所だけでなく、必ず複数の事務所を比較検討することが大切です。



初回無料相談を上手に活用する方法
多くの法律事務所では、「初回相談30分無料」といったサービスを実施しています。
これは、費用を気にせず、弁護士との相性を確認できる絶好の機会ですので、積極的に活用しましょう。
無料相談は、単にアドバイスをもらう場ではありません。
- 弁護士を「面接」する場
あなたの話を親身に聞いてくれるか、難しい法律用語を分かりやすく説明してくれるか、信頼できる人柄か、といった点をご自身の目で確かめましょう。 - 複数の事務所で相談する
複数の弁護士から話を聞くことで、より多角的な視点からご自身の状況を判断できます。
「この先生なら信頼できる」と感じられる弁護士を見つけることが、何よりも重要です。
あなたのエリア(所在地)での検索方法
お住まいの地域で相談できる弁護士を探すには、「離婚 弁護士 〇〇市」や「離婚相談 無料 〇〇区」のように、具体的な地名を入れて検索するのが最も簡単で効果的です。
また、各都道府県の「弁護士会」のウェブサイトには、所属する弁護士の名簿や、相談窓口の案内が掲載されていることが多いです。
弁護士会が運営する公的な法律相談センターを利用するのも、信頼できる専門家と出会うための一つの方法と言えるでしょう。

弁護士を依頼する場合の費用と抑えるコツ
弁護士に依頼する場合の費用は、主に「相談料」「着手金(最初に支払う費用)」「報酬金(成功に応じて支払う費用)」「実費(交通費など)」で構成されます。
費用を抑えるためには、まず、複数の事務所の料金体系を比較検討すること。
そして、ご自身の状況や証拠を事前に分かりやすく整理しておくことで、相談や打ち合わせの時間を短縮し、結果的に費用を抑えることに繋がります。
また、収入や資産が一定の基準以下の方は、費用の立替え制度がある「法テラス」の利用も検討しましょう。


「離婚 相談 窓口」に関するよくある質問
離婚に関する相談窓口の種類や選び方が分かっても、いざ相談となると、「こんな初歩的なことを聞いてもいいのかな…」といった、具体的な疑問や不安が次々と浮かんでくるものです。
人生を左右するかもしれない大きな一歩ですから、慎重になり、様々なことが気にかかるのは当然のことでしょう。
その小さな不安が、相談へのハードルを上げてしまっているかもしれません。
ここでは、離婚相談を検討されている多くの方が抱く、共通のご質問とその答えをQ&A形式で分かりやすく解説していきます。
あなたの最後の一歩を、そっと後押しできれば幸いです。
Q. 相手に内緒で相談することは可能ですか?
A. はい、もちろん可能です。
弁護士や行政書士、カウンセラーといった専門家や、市区町村などの公的機関には、厳格な「守秘義務」があります。
あなたが相談した内容や、相談に来たという事実そのものが、あなたの許可なくパートナーに伝わることは決してありません。
安心してご自身の状況を打ち明けてください。
Q. 相談したら必ず離婚しないといけませんか?
A. いいえ、全くそのようなことはありません。
離婚相談は、あくまであなたの現状を整理し、専門家の客観的な意見を聞くことで、今後の選択肢を明確にするためのものです。
相談した結果、「関係修復に向けてもう一度頑張ってみよう」と決意される方もたくさんいらっしゃいます。
最終的にどうするかを決めるのは、他の誰でもない、あなた自身です。
Q. 電話やオンラインでの相談はできますか?
A. はい、現在では多くの相談窓口が電話やオンライン(Zoomなど)での相談に対応しています。
「仕事や育児で家を空けられない」「近くに相談できる場所がない」という方でも、自宅から気軽に専門家のアドバイスを受けることが可能です。
各窓口のウェブサイトなどで「オンライン相談可」といった表記を確認してみてください。
Q. 家庭裁判所の調停についても相談できますか?
A. はい、もちろん相談できます。
むしろ、それは弁護士への法律相談における、最も重要な相談内容の一つです。
離婚調停を有利に進めるための戦略、申立書の書き方、調停委員への効果的な伝え方、相手の主張への反論方法など、手続きのあらゆる段階について、具体的なアドバイスを受けることができます。
調停を申し立てる前に、一度相談しておくことを強くお勧めします。
Q. 離婚後のアフターサポートはありますか?
A. はい、窓口の種類によっては、離婚成立後のサポートも行っています。
例えば、弁護士に依頼していた場合、離婚後に養育費の不払いが起きた際の強制執行手続きなどを引き続き依頼できます。
また、カウンセラーは、離婚後の新しい生活への適応や、精神的な安定を取り戻すためのサポートを継続してくれます。
公的機関でも、ひとり親家庭向けの支援制度など、離婚後の生活を支える様々なサポートが用意されています。

まとめ:相談窓口で安心の第一歩
この記事で、「離婚相談窓口の種類と特徴」「相談先ごとのサポート内容」などについて説明してきました。
離婚の悩みは誰にも相談できず心細いものです。しかし、無料相談から専門家対応まで、自分に合った窓口を選べば必ず道は開けます。各窓口には得意分野があるため、目的に応じた利用が解決への近道でしょう。
今すぐこの記事を参考に、最適な相談窓口をピックアップしてください。
まずは気軽に問い合わせて、具体的なアドバイスを得る一歩を踏み出しましょう。
経済的な不安や「誰にも話せない…」という孤独感は、専門家への相談で早期に解消できます。無料窓口や法テラスなど、安心して利用できる場所も豊富ですので、ぜひ活用をご検討ください。
正しい相談窓口を利用すれば、不安な気持ちは確かな自信へと変わります。未来の安心した生活を思い描きながら、一歩ずつ進んでいきましょう。
まずは最寄りの市区町村窓口や法テラス、オンライン相談の予約から始めて、新たな一歩を踏み出してください。

専門家に相談するなら「オンライン離婚相談 home」

男女関係や離婚の悩みって、
誰に相談したらいいんだろう…

弁護士やカウンセラーの事務所に
いきなり行くのはちょっと怖い…
\それなら…/
オンライン離婚相談 homeなら
来所不要、あなたのPC・スマホから
さまざまな専門家に相談できます。
夫婦関係や離婚に関する、あなたのお悩みに合った専門家とマッチング。いつでも好きなときにオンラインで相談できます。
夫婦関係の改善、離婚調停、モラハラ・DV、不倫・浮気、別居などさまざまなお悩みについて、専門家が寄り添います。匿名で利用できるため、プライバシーなどを気にせず、何でも安心してご相談いただけます。
24時間365日 オンライン相談できる

ビデオ通話、チャットからお好きな方法で相談いただけます。またプランも、1回ごとや月々定額(サブスク)からお選びいただけます。
厳選された専門家

弁護士、行政書士、探偵、離婚・夫婦問題カウンセラーなどの、経験豊富で厳選された専門家があなたの悩みに寄り添います。
離婚の公正証書が作成できる

離婚に強い女性行政書士に相談しながら、離婚条件を公正証書にすることができます。
公正証書にすることで、慰謝料や財産分与、養育費などが守られない場合、強制執行(給与、預貯金などの財産を差し押さえ)がカンタンになります。
養育費公正証書作成で数万円補助の可能性

養育費を取り決め、実際に受け取っているひとり親は、全体のわずか24.3%にとどまります。
この養育費未払い問題に、各自治体ではさまざまな支援制度が用意されています。
養育費に関する公正証書作成補助として、神奈川県は上限4万円、横浜市は上限3万円、川崎市は上限5万円などです(2025年4月時点)
参考:全国自治体の養育費支援、神奈川県の養育費支援

夫婦関係や離婚に関するお悩みを、24時間365⽇オンラインで解決できるオンライン離婚プラットフォーム。
夫婦関係の修復から、夫婦の話し合い、離婚相談、離婚後のサポートまで、専門家があなたの悩みに寄り添います。






